-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

目次

BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉であり、日本語に訳すと「事業継続計画」です。
大地震等の自然災害や感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、供給網であるサプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化等、非常事態が起こった際でも重要な事業を中断させない、または中断後の早期復旧を目指すために備える方針や体制、手順です。
災害や感染症の拡大など緊急事態が起こった際に被害を最小限にとどめ、事業を継続していくために行う対策のことをいいます。
これからBCPを推進していこうと考えている場合は、以下の流れで進めていきましょう。
はじめに定めておく必要があるのが、基本方針です。BCP対策を行う目的から基本方針を決定していきましょう。
この時、企業理念を軸にするとどのような方針を考えれば良いかわかりやすくなります。
BCPは非常事態でも事業を継続していくための対策なので、そのためにはどの事業を最優先にするか、いつまでに、どのレベルまで復旧させるのか基本的な方針を決定しておくことが欠かせません。
BCP対策を強化するために必要な社内体制を整備していきます。
まず行うべきなのは、経営陣のコミットメントです。不測の事態に会社の経営方針を決めるのは、総務部でもリスク管理部でもなく、経営陣であるためです。
経営陣、取締役会のコミットメントがなければBCPは策定できません。
経営陣のコミットメント、BCPへの理解が済んだ段階で行うのが、計画策定プロジェクトチームの結成です。
その上で誰がどのような役割を持ってBCP対策を進めていくのか決めていきます。
部署を超えてプロジェクトチームを結成することが大切です。旗振り役や、経営陣とコミュニケーションをとる担当者、BCP策定プロジェクトリーダー及び策定後のBCM(事業継続マネジメント)を所管する部署を決めることが大切です。
BCPを文書策定だと認識して総務部がBCP策定をしている企業が多くありますが、その内容の多くが防災計画になってしまっています。BCPはあくまで事業継続計画なので、経営戦略部や秘書室などが旗振り役となることも望ましいです。
部署ごとに担当者を決める場合は部署間で連携して必要なBCPを策定しましょう。
緊急事態が起こった際、どの事業から先に復旧させていくのか決定します。優先させるべき事業を考える際は、会社にとって特に重要な事業や、売上または利益に最も貢献している事業を選ぶと良いでしょう。
これらには該当しなかったとしても、復旧の遅れによって大きな影響が生じる事業がある場合はこちらも優先順位が高くなります。
また、自社に関連した事業ばかり復旧を優先させると、顧客からの評判が落ちてしまう可能性もあるので、このあたりのバランスについても考えていかなければなりません。
すべて早期復帰を目指せば良いのですが、同時復旧しようとすると最も優先したい事業の復旧が遅れてしまうので、優先順位を定めておくことが重要です。
関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素
復旧を優先させる事業が決まったら、事前案を策定するために現在行っている事業ごとの業務を洗い出していきます。その業務の中でどの業務から優先して行う必要があるのか考えて事前案を策定していく形です。
復旧にかかる時間や、事業が停止した場合にどれくらいの期間までなら耐えられるのかなども考えていきましょう。
また、事業の停止が長引けば顧客が離れてしまうことは避けられず、失われた需要はそう簡単には戻りません。顧客が離れてしまうまでにどれだけの期間的猶予があるかも考えておかなければなりません。
BCPの発動基準を明確に検討しておきます。
たとえば、オフィスビルが大きな被害を受けるほどの大地震が発生した場合などはBCPを発動するべきタイミングです。
しかし、そこまで大きな被害を受けていない場合はBCPを発動して良いか判断できないことがあります。
判断が遅れるとそれだけ初動対応も遅くなってしまうことになるので、何かあった際にすぐに対応できるように 発動基準を明確にし、初動対応体制を整備することが不可欠です。
たとえば、BCP発動を判断する主体となる災害対策室などの招集体制(参集レベル)を、3段階程度に分けておく方法があります。
危機事象の内容や発生エリアごとに、軽度と判断される場合は「災害対策準備室」、中度の場合は「災害対策室」、重度の事態では「緊急対策本部」といったように、対応組織をあらかじめ定めておきましょう。
また、BC(事業継続)の対象には自然災害だけでなく、感染症のまん延、地政学リスク、情報セキュリティリスクなども含まれます。
こうしたリスクに対する参集レベルも、BCP上に定めておくことが重要です。
特に、地震や台風等の自然災害に関わるBCP を発動する場合、まずは 従業員や家族の安否確認と被害状況の確認、被害を受けた場合の緊急対応、復旧対応へと進んでいくことになります。
各ステップで誰が誰に対して指示を出すのかも定めておきましょう。
関連記事:BCPで企業の災害対策を強化!対応が欠かせない理由と対策の具体例
BCP対策は 、上層部の人間だけが意識したところでうまくいきません。社内で意識を共有し、全体で取り組む姿勢が求められます。
まずは経営陣が正しくBCPを理解することが重要です。経営陣には、BCPが単なる防災対策ではなく事業継続計画であることを理解してもらい、事業継続の基本的な方針について経営方針を示してもらわなければなりません。
そのうえでBCP策定プロジェクトチームが経営陣に重要事業のヒアリングを行うことにより、事業の復旧優先順位を理解しやすくなります。
次に、BCP策定プロジェクトチームは事業継続に不可欠な経営資源などのリソースの洗い出しを行い、代替戦略を策定しましょう。時には長期的な投資や事業拠点の選定などが必要な場合もあります。
事業継続のためにどれだけ投資ができるのかで、選択できる事業継続対応と重要業務の復旧スピードが変わってくるので、事業継続実現のためには根気強く経営陣や財務部門などと交渉を行うことが大切です。
策定した戦略は問題がないか経営陣に確認してもらいましょう。
事業継続計画に基づく業務の優先復旧については、少なくともマネジメントレベルの従業員が理解しておく必要があります。有事の際に一からBCPを確認していたのでは、迅速な事業復旧を行うことはできません。
例えば「有事の際には自身の事業部の優先復旧順位が高いので、すぐに代替拠点に移る準備を整える」などの対応です。
場合によっては、製品の製造を一定期間協力会社に委託するという迅速な判断が求められることもあります。
マネジメントレベルの従業員がこういった判断を行えるようにBCPへの理解を深めておきましょう。
策定した計画書は、定期的な更新が必要です。
訓練を行う中で現在のBCP対策では不足しているポイントも見えてくるはずです。訓練結果から必要と思われる更新を実施していきましょう。
訓練を企画する立場にある方は訓練が成功することを目標としていることが多いものの、BCP訓練においては訓練の成功を目指す必要はありません。
そもそもBCPの訓練は、不測の事態が発生したときの対応方法を確認しているのです。訓練参加者から「訓練設計の状況付与が不十分」「自分は何をすべきかわからなかった」などのアンケート結果を得ることもあるでしょう。
しかし、訓練の中で「BCP発動時に自分がすべきことがわからなかった」ということが判明しただけでも成果といえます。次の訓練に向けてBCPを読み直したり、事業継続について意見交換したりするプロセスそのものが事業継続力の強化になるからです。
もちろん、訓練の結果判明した改善点や不具合についてはBCPの修正が必要になります。
誰(管掌部署)が、いつまでに修正して経営陣の了承を得るかを事前に決めておきましょう。
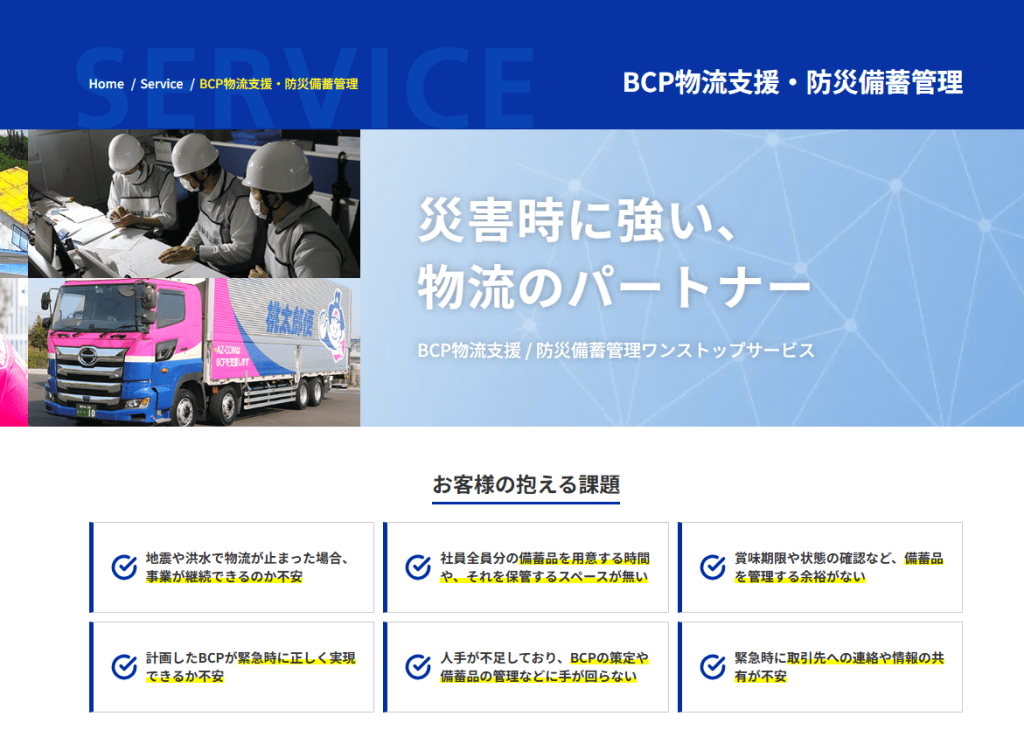
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。
災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。
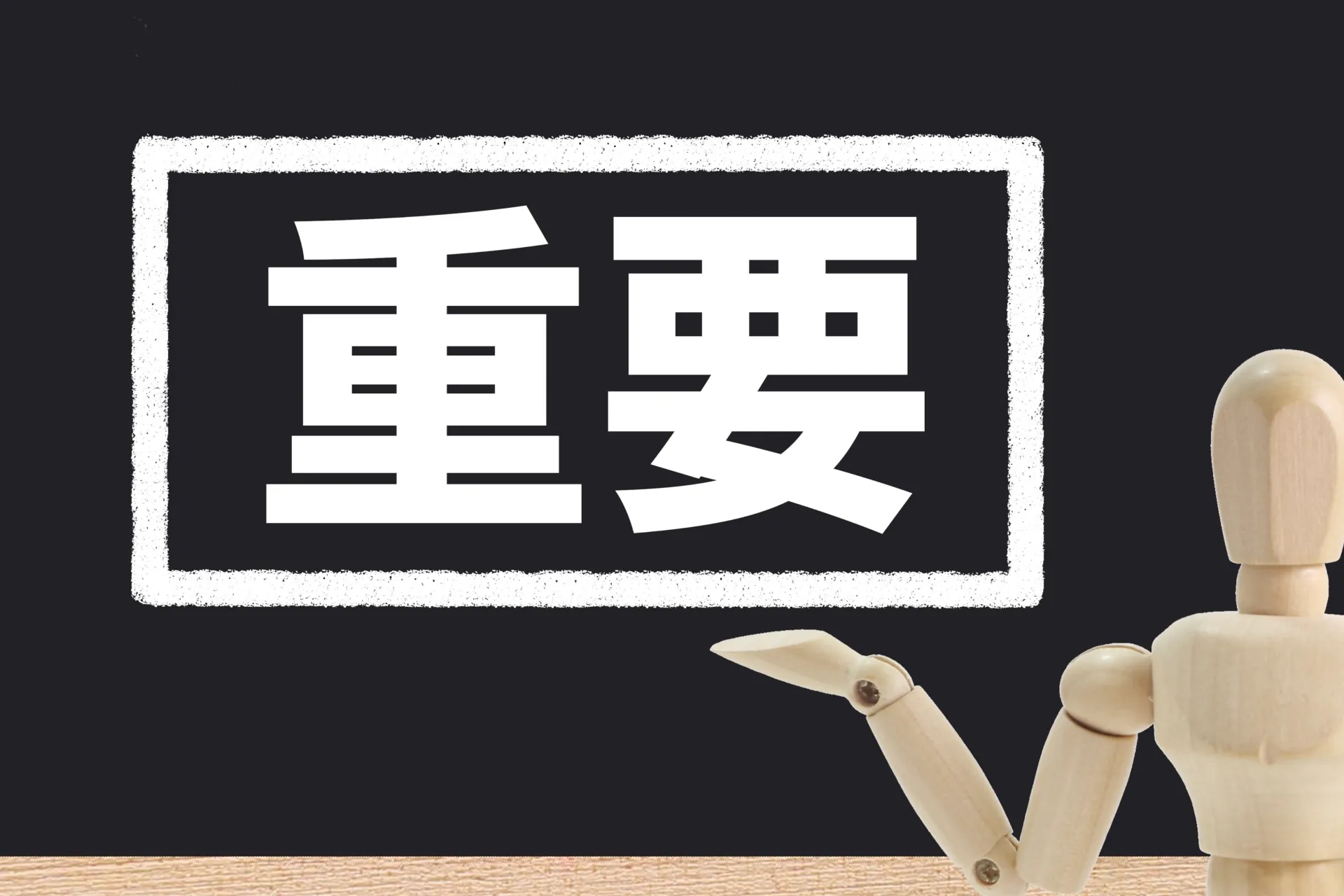
BCP(事業継続計画)は、企業が非常時にも重要な業務を維持・再開するために不可欠な取り組みです。
本記事では、BCP策定の基本的な流れとして、リスクの洗い出しから優先業務の選定、対策の立案・実行、そして継続的な見直しまでのプロセスを解説しました。
日々の業務に追われがちな中でも、万が一に備える姿勢が、企業の信頼と継続性を支える鍵となります。
丸和運輸機関ではBCP物流における「BCP物流支援サービス」・BCP備蓄における「防災備蓄管理ワンストップサービス」を提供しております。
緊急時にもスムーズに物資を届け、必要な備えを確実にサポートいたします。
平時からの準備が、企業の信頼と安心につながるため、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中