-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

近年は自然災害が多く、企業として万が一に備える備蓄品を整備する必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ何を備蓄すればよいのか考え出すと、つい品数が多くなりがちです。
今回は防災士・災害備蓄管理士の資格を持つ佐藤彩乃さんに、必要最低限に品数を厳選して「企業の防災セットに絶対に必要なもの」を解説して頂きます。災害発生直後に必要な備蓄品を4つ、帰宅が困難になった従業員や来訪者が社内で待機するために必要な備蓄品を6つに厳選しました。
目次
・ヘルメット
・手袋・グローブ
災害発生直後、建物から一時避難する際や安全に片付けをする際に必須なのが「ヘルメット、手袋またはグローブです。
特に大きな地震の後は、震度6レベルの余震や、熊本地震のように最初の揺れの後に本震が来る場合がありますので、全従業員分と来訪者分のヘルメットが必ず必要です。
ヘルメットは置き場所に困るものですが、避難の時すぐに取り出せなくては意味がありません。防災倉庫や備品庫にしまい込まず、業務中にすぐに取り出せる場所に備えましょう。最近は折り畳みのヘルメットも販売されています。
最近は自転車通勤の方も多く、自転車通勤用のヘルメットでも代用できると考える方がいるかもしれませんが、基本的に防災・作業用ヘルメットと自転車用ヘルメットは構造が違います。
防災・作業用ヘルメットは「落下物から頭を守る」「転倒した時頭を守る」という役割があります。ヘルメットには、厚生労働省告示第66号「保護棒の規格」により、「飛来・落下物用」(必須企画)と「墜落時保護用」(任意企画)があります。
既定の材料・構造であり、衝撃テストに耐えられるかなどをチェックし、検定に合格した「労・検」ラベルのあるヘルメットを推奨します。
ヘルメットで注意したいのが、使用期限です。プラスチックの劣化などが理由で、およそ6年での交換が推奨されています。
手袋・グローブは割れたガラスを片づけたり、倒れたり傾いたりした什器をもとに戻すのに使います。
企業の防災セットに「最低限」必要なものとして、救助用品を入れました。防災・BCPでは、従業員や来訪客の命が助かることが何よりも大切です。
・バール
・ジャッキ
・ハンマー など
能登半島地震で亡くなった方の死因は「圧死」が4割でした。
阪神淡路・大震災で亡くなった方の死因は「窒息・圧死」が約8割でした。
参考:https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/daishinsai/1.html
救出者のうち、生存者の占める割合については、「早く助けるほど生存の確立が高い」ということが分かっています。
平時の什器固定が必要なのは言うまでもありませんが、バールやジャッキなどがあれば、下敷きになった従業員を救助できる可能性があります。
また、ドアが歪んで開かない、電子キーが停電で開かない間に火災が発生しては大変です。扉をこじ開けたり、間仕切りを壊したりするようなシーンでは、バールやハンマーでガラスをたたき割って脱出する事ができる可能性があります。
大規模災害発生直後は、救急車を呼んでもすぐに到着するとは限りません。
会社にある置き薬などに追加して医薬品も防災グッズに加えましょう。
・AED
・止血に必要なもの(手袋、ガーゼ、包帯など)
・胃腸薬、解熱剤
照明は、「災害発生直後」「3日間の社内待機」どちらのフェーズでも必要な防災グッズです。
・避難用のあかり(懐中電灯)、電池
・帰宅待機 社内宿泊中に必要なあかり(ランタン)
・スマートフォン充電用バッテリー
避難用の明かりは、安全に避難をするためにも必要な防災グッズです。
さらに、帰宅困難の従業員や来訪者を社内で宿泊させるためには手に持つ必要のないランタンなどの灯りが必須です。
従業員・来訪者は、おのおのスマートフォンで安否確認を行ったり、情報収集したりしますから、充電用バッテリーを提供することも重要です。
企業は、帰宅が困難になった従業員や、来訪者を店舗内で待機させる必要があります。
平成23年3月11日の東日本大震災では、鉄道等の運航停止により多くの帰宅困難者が発生し、東京だけでなく多くの地方都市で駅周辺が大混雑に見舞われたことを覚えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、災害発生から3日間は人命救助の生存率が高いため、人命救助が最優先で行われます。災害発生直後に従業員に帰宅命令をすると、会社から帰宅困難者を送り出してしまうこととなり、人命救助の妨げになるでしょう。
帰宅が困難になった従業員や、会社・店舗への来訪者が社内や店舗で待機するために必要な3日分の備蓄品を解説します。
備蓄をしていたものの、使おうと思ったら賞味期限や消費期限が切れていたというケースを防ぎたい方はこちら
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順
一人1日3ℓ×3日分
アルファ化米などを食べられる状態にするための調理用水と飲料水を合わせて、一人1日3ℓ×3日分です。手を洗う水や、トイレを流す水などは含まれていません。
企業備蓄で最低限の備蓄をするならば、2ℓペットボトルで備蓄するのがコスト安でしょう。
一方で、一人当たりに換算すると2ℓペットボトルが4.5本となります。配布をする手間や衛生面を考慮すると、一人当たり500㎖×18本にするか、飲料水と一緒に紙コップなどを備蓄しておくことが望ましいと言えます。
例えば従業員の分は2ℓのペットボトル、来客の分は500㎖のペットボトルで備蓄するなども有効です。
水はローリングストックをしやすい備蓄品なので、ローリングストックで備蓄することをお勧めします。
一人1日3食×3日分
企業備蓄における最低限の食料品備蓄は、「火を使わずに調理でき、スプーンなどのカトラリーを使用しなくても食べられるもの」です。
代表的なのはアルファ化米おにぎりや缶詰のパンです。
災害時には従業員や来訪者が帰宅できずに不安な気持ちで会社内に滞在する為、食事は「楽しみ」にもなり得ます。
おかゆやアルファ化米などの主食のほかにも、1日1食でも甘いもの(ようかんは保存期間が長くてお勧め)や、ナッツ・ドライフルーツ等でタンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルを補給できるといいですね。
また、従業員や来訪者に要配慮者がいる場合には備蓄品も配慮しましょう。特に要配慮者までの企業備蓄をしている企業は多くない為、平常時の顧客が下記に当てはまる企業は、備蓄品提供を通じて顧客の信頼を勝ち取るチャンスです。
企業備蓄における要配慮者
・乳幼児
・高齢者
・宗教上の理由で食事制限がある方
・食物アレルギーの方
乳幼児向け備蓄食料の例
・液体ミルクと使い捨てほ乳瓶(粉ミルクはお湯が必要。企業備蓄には向かない)
・離乳食用のレトルト食品
高齢者向け備蓄食料の例
・おかゆ
・ゼリー飲料
宗教上の理由で食事制限がある方向け備蓄食料の例
・ハラール認証の備蓄品
ハラール対応の災害用備蓄品も販売されています。自治体の備蓄でも頻繁に見かけるアイテムです。
食物アレルギーの方でも食べられる備蓄食料の例
・米粉クッキー
米粉のクッキーは、小麦粉や卵、乳製品などを使用せずに作られています。
東日本大震災時、各地の避難所では保護者の目の届かないところで食物アレルギーの子が誤って食べたものでアレルギー症状を起こし、救急搬送されるなどの事態が起きました。内閣府は、避難所の備蓄品に食物アレルギーの方に配慮するように呼び掛けています。
一人当たり1日5回使用×3日分
企業の防災セット、備蓄品における最低限の備蓄アイテムとして必須なのが簡易トイレです。トイレは我慢のしようがありません。
例えば地震や大雨が発生した際に、一見被災が無いように見えるトイレでも、設備の被災が無いことを調査し終えるまでは水洗トイレは使用してはいけません。下水道管の破損による逆流や、断水が想定されるからです。
万が一、下水道管が破損しているのに水洗トイレを使用し続けた場合には逆流し漏れ出す可能性があります。
最低限の備蓄アイテムとして用意するのに保管スペースが少なく手軽なのが、便器設置・凝固タイプの簡易トイレです。便座がある場所ならどこでも使用でき、衛生面やにおいの心配が少なく用を足せるのが特徴です。いつもと同じ環境でトイレを使用できるため、心理的な負担が少なく使うことができます。
一方で、便器が破損していたり、トイレに立ち入れない状態になったりしている場合は使用できない為、携帯トイレや組み立て型のトイレも一定数あると安心です。設置の際には避難者20人に対して1基、女性用は男性用の3倍を設置します(スフィア基準)。
衛生用品最低限の企業防災衛生用品グッズを5点に厳選します。
・消毒液
トイレの後の手洗いの代わりに。食事前の手洗いの代わりに。
・マスク
社内宿泊時の、ほこりや粉じんの吸い込み防止。感染予防に。歯みがきができない状況下での口臭・口元の衛生維持に。
・清拭(せいしき)用ボディーシート
汗をたくさんかく夏場の避難生活には必須。集団での避難生活では匂いにも配慮が必要です。
・カイロ
冬場の避難生活に必須。多めに用意しておけば、カイロで温めた食料を食べることができます。
・生理用品
最低限の量は昼用を1日当たり4~5枚×女性従業員数。
経血の多い方は2枚重ねて使用で夜用ナプキンの代わりになります。そのほか、生理の時期でなくても下着の衛生を保つのに使用可能です。
自分の会社で今から3日間宿泊するとして、どこで寝るでしょうか?
デスクで眠る、休憩室のソファで眠る等が考えられますが、そうでない場合の必要最低限の企業備蓄はアルミシート、耳栓、アイマスクです。
毛布や寝袋、避難用マットやダンボールベッドがあればより快適なのは言うまでもありません。
ラジオ、ラジオを動かすための電池など
インターネット不通や、スマートフォン電池切れの状況に備えて、ラジオがお勧めです。
帰宅困難者は、常に「自宅は被災していないか」「家族は無事なのか」「いつになったら帰れるのか」が気になるものです。
万が一の事態が発生した際の備えを充実させておきたいと考えている方はこちら
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。
「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。
企業の備蓄品に必要な最低限の防災セット10選を解説しました。
企業の防災セットの備えには、まずは備蓄品を購入するための予算や保管スペースが必要です。そして現状の備蓄品数量や期限を確認する必要があったり、備蓄品販売事業者から相見積もりを取得したりするなど、購入までのプロセスも煩雑です。
企業の防災セット、災害備蓄品のことなら、丸和運輸機関のあんしんストックにお任せください。従業員1人分の備蓄品をひと箱にまとめて納品するサブスクリプション防災備蓄です。どんな備蓄を備えるべきかのご相談も承っています。
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
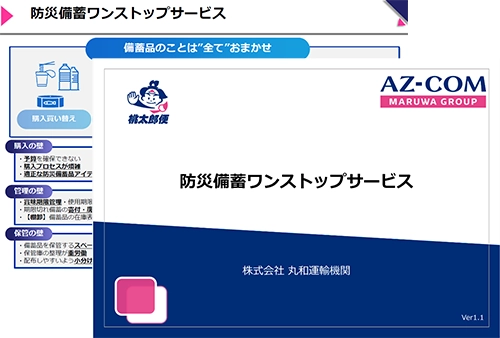 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中