-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

企業のBCP対策を検討している方に向けて、備蓄品リストをご紹介します。
いつ起こるともわからない災害に備えて、BCP対策を整えようとしている、企業の管理職・経理部の方は多いはずです。しかし実際に準備しようとしても、何から準備すべきなのか、どのようなものを準備すべきかと迷ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、BCP対策における備蓄品リストをご紹介していきます。参考にしていただければ、どのような備蓄品をどれだけ準備すべきか、従業員数から割り出すことが可能になります。
目次

企業にとってBCP対策により備蓄を行うことは、「努力義務」とされています。
東日本大震災などの大災害の影響を受け、東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」が策定されました。
そこで努力義務となったのが、従業員1人あたり最低3日間、事業所内に留まれるようにするための備蓄品の保管です[1]。
従業員全員が施設内に3日間滞在しても困ることがないように、被災時に必要な備品を蓄えることが推奨されています。
努力義務であるため、法的な義務ではありません。
しかし発災時には交通機関が停止して、帰宅できない従業員もいることでしょう。
備蓄品を用意しておくことは企業にとって、従業員の健康や安全を確保するために欠かせません。
従業員1人あたりに必要な備蓄品はどれくらいであるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
【従業員1人あたりに必要な3日間の備蓄品[2][3]】
飲用水と調理などに使用する水、そして食料品は必要不可欠な備蓄品です。その他、断水したときのために、簡易トイレも用意しておきましょう。
簡易トイレ以下の品は、必要に応じて備えるべき量を計算してください。女性が多いようなら衛生用品は多くいるでしょうし、乾電池は懐中電灯や携帯ラジオの数によって必要量が変わります。また怪我を負う人がいることも考え、救急医療薬品類は十分な量を用意しましょう。

BCP対策を行うと、従業員だけでなく企業にとっても複数のメリットを享受することが可能です。
しかし実際に有事に遭遇していなければ、どのような効果があるのかと疑問を持たれる方もいるかもしれません。
そこで企業にとってのBCP対策のメリットについて3つの観点からご紹介します。
BCP対策の具体的なメリットや注意点について詳しくまとめた記事はこちら
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?取り入れるメリットと確認すべき注意点
まずは従業員のモチベーションアップにより、業績が向上しやすくなることです。
企業がBCP対策における備蓄品リストを意識していることは、従業員を大切にしているということにほかなりません。企業から大切に扱われていると考えられれば、従業員の意欲の向上が期待されます。企業への帰属意識や貢献意識の向上にもつながります。
日頃からBCP対策を意識することにより、業績向上も期待できます。
従業員のモチベーションをより高めたいと思われるなら、BCP対策に力を入れるのもひとつの方法です。
事業継続性の向上も、BCP対策の大きなメリットの一つです。BCP対策を実践すると、有事の際にも迅速に事業を再開することが可能になります。
たとえば大震災が起きたときは、どのように行動すべきか判断に迷うことも想定されます。
しかしBCPが策定されていれば、取るべき行動や事業を再開させる方法、優先すべき事業などが明確になります。そのため事業を継続しやすくなるでしょう。
さらに平常時でも優先すべき業務が見えてくるはずです。BCP策定を通して自社にとって重要性の高い事業が浮き彫りになることで、経営戦略の見直しにもつながります[4]。
災害などが起こらなかったとしても、事業継続性の強化につながることも、BCP策定のメリットです。
BCPの策定には、企業イメージを向上させる効果も期待できます[4]。緊急事態が起きたとしても、事業を継続できる体制が整っている企業であると認識されるためです。
たとえばBCP対策を万全にしている取引先と、全く行っていない取引先があったとしたらどう思われるでしょうか。有事の際にも事業を継続できるように体制を整えている取引先の方が、信頼できると感じられるはずです。
もちろん顧客や株主から見ても、BCPを策定している企業の方が信頼性は高いと考えられる可能性があります。
以上のようにBCP対策は自社や従業員を守るものであるとともに、企業イメージ向上にも貢献してくれるものです。

BCPを策定することにはさまざまなメリットがありました。しかし策定するとしても、どのような備蓄品を準備すべきか迷う方もいると考えられます。
そこで災害発生時の初動対応用の備蓄品リストについて解説します。
BCPを策定するなら、初動対応用として下記の備蓄品リストを参考にしてください。
企業の防災グッツについて詳しく紹介している記事はこちら
関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選
まず準備したいのは、災害の情報を収集するためのグッズです。
【備蓄品リスト】
現代ではスマートフォンで情報収集ができます。そのために必ず準備しておきたいのが、充電用の予備バッテリーです。スマートフォンが使用できなくなると、家族との連絡も取れなくなってしまうかもしれません。その他の製品に充電する可能性も踏まえて、できる限り大容量のバッテリーを用意してください。
しかしインターネットやSNSの情報は、必ずしも真実であるとは限りません。正確な情報を確保するために、携帯ラジオや簡易的なテレビも情報源として準備しておきましょう。
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
大災害が起きたときに備えて、安全用グッズの備えも不可欠です。たとえば大震災が起きた場合、二次災害が起きることも考えられます。
さまざまな状況を想定して、必要な安全用グッズを事前に準備しておくことが推奨されます。
具体的には次のようなものが必要となります。
【備蓄品リスト】
ヘルメットや軍手、非常用ライト、安全靴等は倒壊した建物の中で行動するときの身の安全を守るために必要となります。ホイッスルやブザーがあれば、助けを求めるために活用できるでしょう。
メガホンがあれば安否確認の呼びかけや避難行動の誘導に活躍します。
また地図や自転車があれば、交通機関が麻痺したときでも移動できます。必要なときに備えて、少量準備しておくと心強いでしょう。
負傷者がいたときのために、救助用・救護用グッズも事前に準備しておく必要があります。
【備蓄品リスト】
工具類は家具や建物が倒壊して、下敷きになってしまった人の救命に役立ちます。ドアや窓が開かなくなってしまったときにも使えるでしょう。
そして負傷者のために、救急グッズも備えてください。消毒液や包帯、ガーゼなどがあれば、助けが来るまでの応急処置に使えるはずです。
BCPが実践されるような大きなできごとが起きた場合、負傷する人はいると考えられます。人命救助のための救助用グッズ、救護用グッズを準備し、使い方の習得も事前に行うことが望まれます。
関連記事:医療機関におけるBCPとは?検討すべき要素や策定する際のポイント

災害などが発生した場合に備えて、3日間分の備蓄品の準備を企業の努力義務としています[1]。しかし3日分とはどのくらいの量になるのでしょうか?
そこで3日間待機するために必要な備蓄品リストをご紹介しますので、BCP策定の参考にしてください。従業員1人あたりに対して必要な量を掲載します。
災害時に必要になるものと防災リュックに入れておくものについて詳しく知りたい方はこちら
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
「水は生命維持に不可欠な資源です。保存水は1人あたり1日3Lと言われています[2]。3日間であれば1人あたり9Lの水が必要です。しかし1人が必要な最低限の飲料水の量は1日あたり1L[3]。
余裕を持たせて、1日あたり1.5Lの飲料水と、1.5Lの調理用水を準備しておけば適切と考えられます。
災害が起きた直後は断水となることも珍しくありません。水が供給されなくなれば脱水症状になったり、食事が摂れなかったりなどの事態が発生する可能性もあります。
BCP備蓄品リストには、必ず「1人あたり3日間で9Lの水」を含めるようにしてください。
食料品は1人あたり、3日間で9食分を備えるようにしましょう[3]。人が生きるために、水と同じくらい優先的に備えるべき備蓄品の一つです。
食料品を用意する際には、主食は「米」を中心とすることをおすすめします。米はエネルギー源となり、調理がしやすく、保存しやすいことも利点の一つです[3]。
ただし米だけでは栄養が偏ってしまうため、ビタミンやミネラル、食物繊維を補充できるように、保存期間が長くすぐに食べられる缶詰を副食として用意しておきましょう[3]。
カセットコンロや調理器具、燃料、調味料も用意しておくと、調理の幅が広がるはずです。
備蓄の際の際には賞味期限の確認を定期的に行うことが必要です。
BCPの備蓄品リストには、衛生用品も含める必要があります。たとえば次のようなものが該当します。
【衛生用品の備蓄品リスト】
災害時には簡易トイレを中心に利用するかもしれません。しかしいざというときのために、トイレットペーパーも準備しておきましょう。
衛生管理の観点からも、マスクや歯ブラシの備蓄は必要とされます。
そして女性にとっては必要不可欠な衛生用品である生理用ナプキンも備蓄しておくことが重要です。
避難生活で不自由を感じないようにするには、衛生用品の備蓄は不可欠です。最低限の準備をしておくようにしてください。
季節によって防寒グッズの備蓄は、体調不良の予防に効果的です。防寒グッズがないと風邪や免疫力の低下による体調不良のリスクが高まる可能性があります。
次のようなものを準備しておきましょう。
【備蓄品リスト】
ブランケットや毛布、防寒シートは寒さを凌ぐ効果があり、さらに快適性の確保にも寄与します。もしなければ新聞紙や段ボールも防寒対策として使えるでしょう。
BCPが実践されるときは突然やってきます。季節ごとの気温変化を踏まえて、BCP備蓄品リストの内容を検討することが求められます。

もしもの災害のときのためにBCPを策定したり備蓄品リストを整備したりする前に、対応すべきことがあります。次の4つのポイントを押さえて、適切なBCP対策を行えるようにしてください。
まずはBCPを策定する目的を確認しましょう。「なぜBCPを策定するのか?」と考えてみてください。
策定の主な目的は、「人命を守るために必要な備蓄品の確保」です。しかし企業によっては、顧客からの信用の維持や売上確保を目的とする場合もあります[5]。
自社におけるBCPの目的を明確にすることにより、備蓄品のリストが変わってくることもあるでしょう。
まずは目的を明確にし、目的に合わせた整備を行ってください。
人命を守るための備蓄品ですから、従業員数に合わせて必要な備蓄量を把握しなければなりません。従業員数が5名の企業と100名の企業とでは、当然、備蓄すべき物品の量は変わります。
災害時に企業内に在籍している可能性のある従業員数を想定し、予備数を含めた数を算出しましょう。
BCP策定の前に、リストに記載された備蓄品の使用場面を事前に想定しておくことが重要です。必要な場面によって保管すべき場所が変わる可能性があるためです。
たとえばヘルメットであれば、震災が起きた直後、避難する際に使用すると考えられます。すぐに手に取れる場所に収納すべきでしょう。
一方食品や防寒具などは避難をした後に使用するものであり、奥まった場所に保管されていても問題ありません。
備蓄品を使用する場面を想定すれば、保管すべき場所も判断しやすくなります。
BCP対策で備蓄品リストを作成したとして、忘れがちであるのがゴミの保管についてです。災害などが起きた直後は、ゴミの回収が停止されるため、ゴミを保管する場所や方法について検討しておく必要があります。
人が避難している場所にそのまま保管すれば、衛生面や悪臭が問題になるかもしれません。
あらかじめゴミをどこに、どのようにして保管するかを決めておきましょう。

BCP対策の一環として備蓄品リスト整備を検討しているなら、「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」がおすすめです。
備蓄品の保管・管理から輸配送まで、ワンストップで対応できるサービスです。
備蓄品を準備しようとしても、保管場所の確保が難しいこともあるでしょう。「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」では物流倉庫を運営した経験を活かし、備蓄品を適切に管理いたします。
また管理業務負担を軽減できるサブスクリプションメニューであるため、備蓄品管理のための手間も省けるでしょう。
BCP策定にて備蓄品リストを作成しようと検討されているなら、ぜひご活用ください。
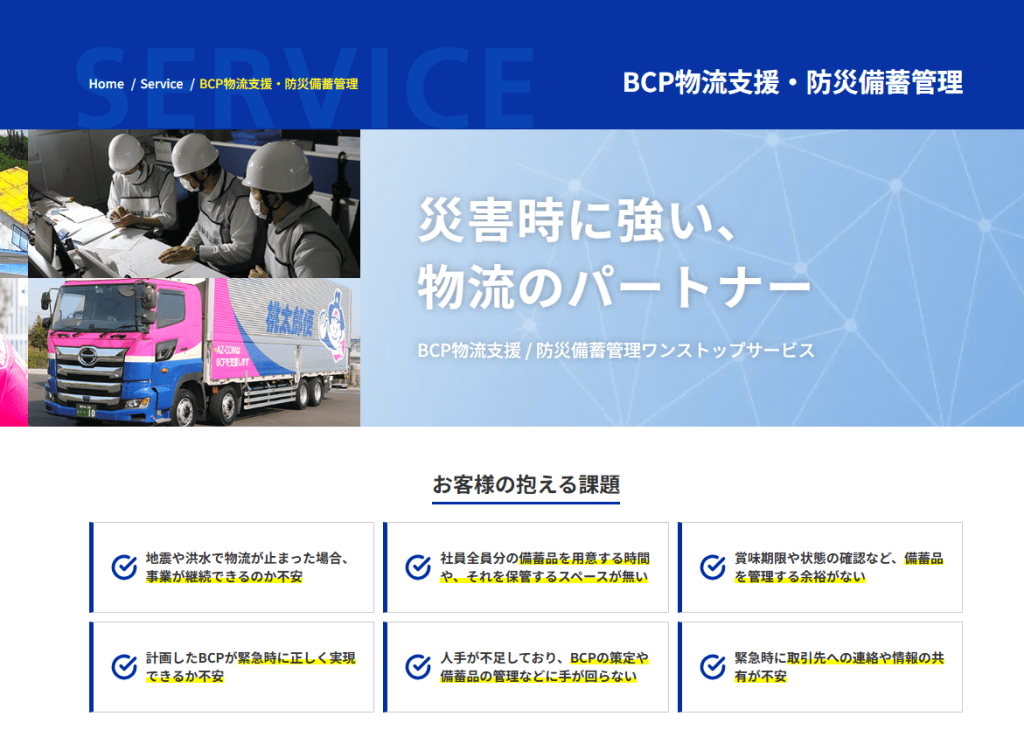
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。
災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、BCP対策における備蓄品リストについてご理解いただけたと思います。BCPを策定するなら、まずは災害から3日間における努力義務とされている、備蓄品のリストを作成してみてはいかがでしょうか。
丸和運輸機関ではBCP対策における備蓄品のことをすべてお任せできる「防災備蓄ワンストップサービス」を提供しています。どんな備蓄品をいくつ購入するべきか、また防災備蓄購入予算の確保が難しいといった企業の防災を担当する方におすすめのサービスです。
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する
「BCP物流支援サービス」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
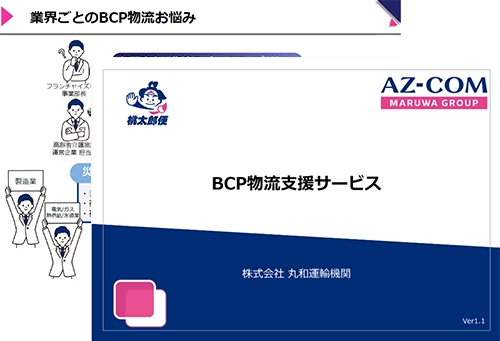 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
[1]
[2]
参照:防災情報のページ:(PDF)補助金に関するお問い合わせを受付ています!
[3]
参照:農林水産省:(PDF)発災当日から1週間分の備えについて基本的な考え方
[4]
参照:BCPはじめの一歩事業継続力強化計画をつくろう!:BCP策定のメリットまとめ。平時にもある意外なメリットも紹介
[5]
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中