-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

大規模災害の発生が予想されているため、オフィスにおいても防災備蓄品の必要性が高まっています。
具体的に、どのようなものを用意すればよいかわからないと考えている方もいるでしょう。
おすすめの備蓄品として、水、食料、救急箱、脱出用工具セット、生理用品などが挙げられます。
実際に用意する備蓄品は、オフィスの特徴などを踏まえて選択することが重要です。
ここでは、企業が備えておきたいおすすめの備蓄品を紹介するとともに、オフィスに備蓄品を置く理由、備蓄品を管理する際に意識したいポイントなどを解説しています。
緊急時の対応を検討している方は、参考にしてください。
目次
 大規模災害をはじめとする緊急事態を乗り越えるため、内閣府は企業に防災対策の強化を呼びかけています。
大規模災害をはじめとする緊急事態を乗り越えるため、内閣府は企業に防災対策の強化を呼びかけています。
災害が発生すると、企業の経営資源であるヒトとモノの安全が脅かされるためです。
たとえば、地震によって交通網が麻痺し、帰宅を断念してオフィスに留まる帰宅困難者が発生する可能性があります。
このようなケースでは、オフィスに備蓄品がないと、従業員の安全を確保できません。
法律で備蓄品の確保を義務づけられているわけではありませんが、備えを怠ると労働契約法第5条で定められている「労働者の安全への配慮」を欠いているとみなされる恐れがあります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
ヒトとモノの被害を軽減して、中核事業の継続・復旧を容易にするため、オフィスに備蓄品を置いておくことが大切です。
内閣府は「事業継続ガイドライン」で、企業が参考とするべき備蓄品の品目・数量を以下のように示しています。
備蓄品の品目及び数量については、企業・組織の拠点が所在する地域の地方公共団体が制定する条例等を参考とし、企業特性に応じた備蓄方法を検討する。
まず、オフィス所在地の自治体が定める条例等を確認しておくことが重要です。
参考に、東京都帰宅困難者対策条例の規定を紹介します。
事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
東京都が発表している「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」で、以下の備蓄品目が例示されています。
【備蓄品リスト】
東京都防災ホームページ「東京都帰宅困難者対策ハンドブック(令和5年3月 東京都)」
以上を参考に、オフィスの特徴などを踏まえて、必要な備蓄品を検討するとよいでしょう。
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順

ここからは、企業が用意しておきたいおすすめの備蓄品を紹介します。
従業員の安全を確保するため、人数分のヘルメットを用意しておきましょう。
発災時に、棚の上に置いていたものが落ちてきたり、照明が落下したりすることが考えられるためです。
ヘルメットを用意しておけば、従業員の頭部を保護できます。
備蓄する際に課題になりやすいのが保管場所です。
保管スペースが十分でない場合は、折り畳み式のヘルメットの導入を検討するとよいでしょう。
折りたたむことで厚みが抑えられ、保管スペースの節約につながります。
脱出用工具セットは、解体作業や撤去作業などに使用する工具のセットです。
できれば準備しておきたい備蓄品といえるでしょう。
大規模災害などが発生すると、什器の転倒や建物の倒壊で、避難経路が塞がれることがあるためです。
脱出用工具セットを用意しておけば、このようなトラブルに対応しやすくなります。
セットになっている工具は、商品で異なります。
オフィスの特徴や想定されるトラブルなどを踏まえて、脱出用工具セットを選びましょう。
救急箱も必要性の高い備蓄品といえます。
発災時に、怪我人や病人が発生する恐れがあるためです。
交通状況、道路状況などによっては、救急車の到着に時間がかかります。
救急箱を用意しておけば、最低限の手当てや応急処置を行えます。
定期的に救急用品の使用期限を確認して、必要があれば入れ替えることも大切です。
医薬品の使用期限は、製造日から3~5年程度に設定されています。
また、誰でも使えるように、保管場所を周知しておきましょう。
従業員がオフィス内に留まれるように、水と食料も用意しておかなければなりません。
備蓄量の目安は以下のとおりです。
| 備蓄品 | 具体例 | 備蓄量 |
| 水 | ペットボトル飲料水など | 3リットル/日×3日分=9リットル |
| 主食 | アルファ化米、カップ麺、レトルト食品など | 1日3食×3日分=9食 |
災害発生から3日間は、救助および救命活動が優先されます。
従業員の一斉帰宅でこれらの活動を妨げないように、3日分の水と食料を用意しておく必要があります。
発災時の来客対応を想定し、備蓄量には10%程度の余裕を見込んでおくと効果的です。
簡易トイレも、用意しておきたい備蓄品のひとつです。
大規模災害が発生すると、水道や電気が止まって既存のトイレを使えなくなることがあります。
尿意や便意は、災害とは関係なく生じます。
我慢し続けることはできないため、従業員数分の簡易トイレを用意しておくことが大切です。
消臭剤や保管用のビニール袋などもあわせて準備しておくとよいでしょう。
使用済みの簡易トイレの保管場所についても、事前に検討しておくことが重要です。
毛布も重要な備蓄品の一つに数えられます。
停電が発生すると、空調設備を使用できないためです。
オフィス内の温度が下がってしまう恐れがあります。
このような事態に備えて、従業員数分の毛布を用意しておきましょう。
保管場所の確保が難しい場合は、毛布の代替として保温シートの活用を検討しましょう。
コンパクトに収納できるため、広い保管場所を確保する必要がありません。
ゴミ袋も可能であれば備えておきたい備蓄品の一つです。
さまざまな用途で活用できるためです。
主な用途として以下のものが挙げられます。
【ゴミ袋の用途】
工夫次第で多様な用途に対応できます。
もしもに備えて、保管しておくとよいでしょう。
ブルーシートも、あると便利な備蓄品です。
ゴミ袋と同じく、さまざまな用途に活用できます。
主な用途は以下の通りです。
【ブルーシートの用途】
ブルーシートがあると、オフィスの快適性を高められる可能性があります。
想定される使用目的に応じて、適切なサイズや厚みを選定することが重要です。
女性従業員がいる場合は、生理用品も用意しておきましょう。
備蓄量の目安は次の通りです。
| 生理用品 | 備蓄量 |
| ナプキン | 5~7枚/日×3日間=15~21枚 |
| タンポン | 3~4本/日×3日間=9~12本 |
経血の処理が困難になると、女性従業員が清潔さを維持しにくくなる可能性があります。
また、生活の質(QOL)も著しく低下する可能性があります。
下着を洗濯できないこと、お風呂に入れないことを想定して、パンティライナーやデリケートウェットシートも用意しておくことをおすすめします。
衛生用品も、忘れずに用意しておきたい備蓄品です。
主な衛生用品として以下のものが挙げられます。
【衛生用品の例】
ウェットシートがあれば、手だけでなく顔や体の汚れも清拭でき、衛生を保ちやすくなります。
歯磨きセットは、できれば水を使わないものを選びましょう。
水を自由に使用できるとは限らないためです。
必要最低限の医薬品も用意しておくことをおすすめします。
発災直後は、医療機関を利用できない恐れがあるためです。
一方で、環境の変化により従業員は体調を崩しやすくなります。
辛い症状を緩和するため、以下の医薬品などを揃えておきましょう。
【医薬品の例】
持病により常用薬が必要な従業員には、緊急時を見据えて予備の薬を携帯するよう促すことが重要です。
発電機やモバイルバッテリーも、重要な備蓄品の一つと考えられます。
停電によりスマートフォンの充電が切れると、情報収集や安否確認が困難になるためです。
ちなみに、携帯電話の基地局は予備電源を備えているため、停電時でも多くの場合、数時間から24時間程度は稼働を継続できます。
従業員が現在の状況を正確に把握できる環境を整えておくことが重要です。
 続いて、備蓄品の管理で意識したいポイントを解説します。
続いて、備蓄品の管理で意識したいポイントを解説します。
水、食料品、医薬品などには、賞味期限や消費期限が設けられています。
備蓄する際に、これらを確認しておくことが大切です。
確認を怠ると、発災時に期限切れで活用できない恐れがあります。
管理の抜けや漏れを防ぐために、備蓄品リストを作成し、賞味期限や消費期限を一元管理することが望ましいです。
備蓄品を保管する場所にも注意が必要です。
特定の環境を避けて保管しなければならないものもあります。
たとえば、フリーズドライ食品を高温の場所に保管すると、劣化を招く恐れがあります。
また、発災時に速やかに利用できる場所に保管しておくことも大切です。
保管場所によっては、いざというときに備蓄品を取り出せないことも考えられます。
備蓄品の定期的な点検も欠かせません。
放置すると、賞味期限や消費期限の切れや備蓄品の劣化につながるおそれがあります。
使用できなくなる前に、新しいものと入れ替えることが大切です。
備蓄品のリストをあらかじめ作成しておくことで、入れ替え作業を円滑に進められます。
 BCP対策は、緊急事態に備えて予め定めておく対策、計画といえるでしょう。
BCP対策は、緊急事態に備えて予め定めておく対策、計画といえるでしょう。
主な目的は以下の通りです。
【BCP対策の目的】
ここでは、BCP対策により企業が得られるメリットを紹介します。
BCP対策に取り組むと、従業員のモチベーションを高められる可能性があります。
従業員を大切に扱っていることを伝えられるためです。
たとえば、大規模災害に備えて従業員用の食料を備蓄すると、自社に対する帰属意識や貢献意欲を高められるでしょう。
BCP対策に積極的に取り組むことで生産性の向上も目指せます。
BCP対策の主な目的は、緊急時における中核事業の継続性を高めることです。
この目的を達成するために、以下の取り組みなどを行います。
【BCP対策の取り組み】
以上の取り組みを行うため、緊急時でも中核事業の継続や早期復旧が可能となります。
経営基盤が脆弱な中小企業にとって、メリットの大きな取り組みと考えられます。
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順
BCP対策により、自社の信用力も高められます。
取引先や見込み客へ、大規模災害などに備えていることを示せるためです。
信頼して取引できる企業として評価される可能性が高まります。
BCP対策に取り組むことで、競合他社との差別化にもつながります。
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。
「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。
 ここでは、企業が備えておくべき備蓄品について解説しました。
ここでは、企業が備えておくべき備蓄品について解説しました。
大規模災害の発生が懸念される中、企業においても備蓄品の重要性が増しています。
おすすめの備蓄品として、水、食料品、ヘルメット、毛布、救急箱などが挙げられます。
自社での備蓄品の確保や管理が困難な場合は、丸和運輸機関への相談をご検討ください。
平時の防災備蓄管理を一括サポートする「防災備蓄管理ワンストップサービス」や防災備蓄品をサブスクリプション形式で提供する「安心ストック」などをご利用いただけます。
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
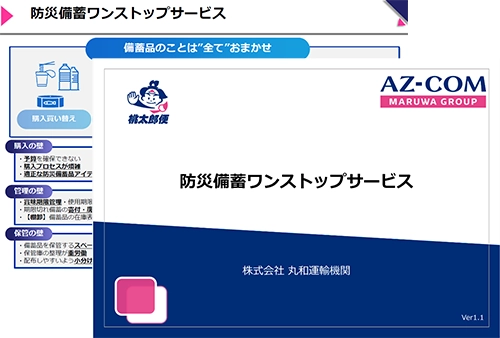 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中