-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

必要な災害備蓄品がわからず、悩んでいませんか。
用意すべき物品が多岐にわたるため、対応に困るケースが少なくありません。
災害備蓄品の役割や用途を理解すると、必要性の高いものを見極められます。
ここでは、企業における防災備蓄品の必要性や選び方を解説するとともに、必要性の高い防災備蓄品の見極め方、災害が発生する前に行っておきたい取り組みなどを紹介しています。
無駄のない準備を進めるための参考資料としてご活用ください。
目次

企業も災害備蓄品の準備が必要です。
労働契約法で、労働者への安全配慮について以下のように定められています。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用:e-GOV法令検索「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
災害備蓄を義務づけられているわけではありませんが、対策を怠ると必要な配慮を欠いたとみなされる恐れがあります。
また、災害備蓄品を準備することで、経営資源であるヒトを守れるため、事業を継続、復旧しやすくなります。
企業にとって欠かせない取り組みと位置づけられます。
現実的な災害として想定されているのが大規模地震です。
ライフラインが被害を受けることも考えておかなければなりません。
復旧にかかる日数は、災害備蓄の量を検討する際の参考になります。
中小企業庁が想定しているライフラインの復旧にかかる日数は以下の通りです。
| 震度 | 水道 | ガス | 電気 |
| 震度6弱 | 7日 | 15日 | 1日 |
| 震度6強 | 15日 | 30日 | 2日 |
| 震度7 | 30日 | 45日 | 4日 |
出典:中小企業庁「資料16 財務診断モデルにおける緊急時被害想定方法 (3) 復旧日数」
具体的な日数は、地震の規模などで大きく異なります。
これらの想定日数を目安として、備蓄量を検討することが重要です。
ちなみに、内閣府は「事業継続ガイドライン」で、企業の備蓄量について以下のように定めています。
備蓄品の品目及び数量については、企業・組織の拠点が所在する地域の地方公共団体が制定する条例等を参考とし、企業特性に応じた備蓄方法を検討する。
東京都が「東京都帰宅困難者対策条例」で定める備蓄量は、従業員の3日分の食料、飲料水、その他必要な物資です。
まずは、自治体が定める備蓄量を確認することが重要です。
出典:(pdf)東京都防災ホームページ「東京都帰宅困難者対策条例」
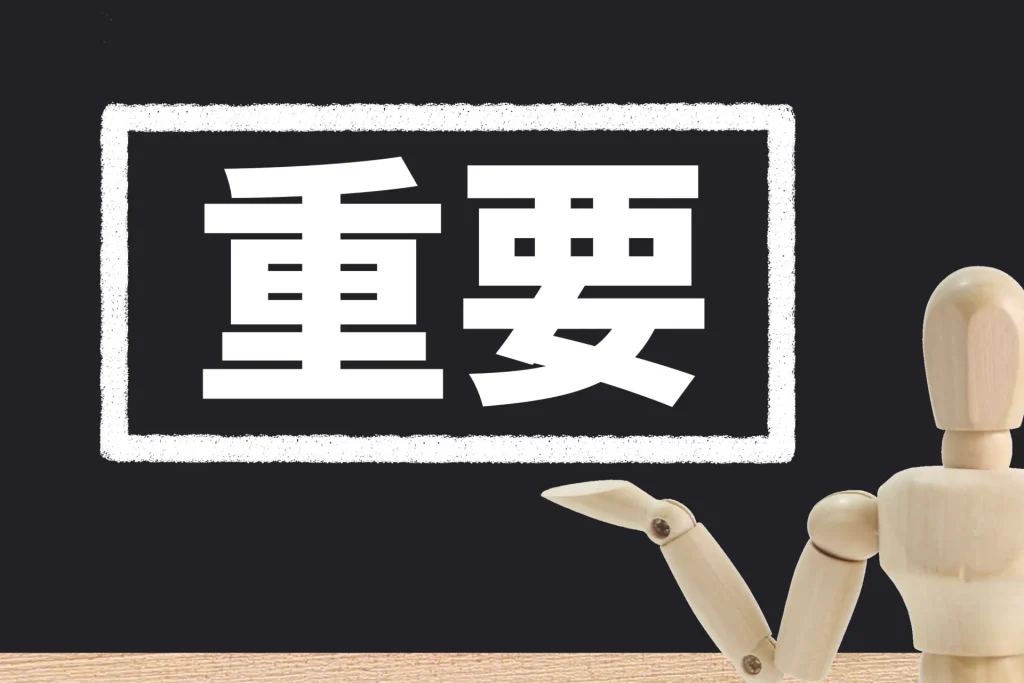
企業が災害備蓄品を選ぶときに意識したいポイントは以下の通りです。
企業が備えるべき主な災害として以下のものが挙げられます。
【企業が備えるべき主な災害】
災害の種類により想定されるリスク、必要性の高い災害備蓄品は異なります。
たとえば、地震では飲料水や食料、感染症ではマスクやアルコール消毒液の必要性が高いといえるでしょう。
災害の種類とリスクを踏まえたうえで、災害備蓄品を選択することが大切です。
大規模災害では、想定外の事態が起こりえます。
万が一に備えて、さまざまな災害備蓄品を用意しておきましょう。
具体的な災害備蓄品の例は以下の通りです。
【災害備蓄品の例】
詳しくは「災害備蓄品で必要なもの」で解説します。
また、必要量をチェックしておくことも重要です。
備蓄量が不足していると、従業員にいきわたらない恐れがあります。
1人あたりの備蓄量の目安は最低3日分を基本としています。
| 災害備蓄品の種類 | 備蓄量の目安 |
| 飲料水 | 1日3L×3日分=9L |
| 食料(主食) | 1日3食×3日分=9食 |
来客などを想定し、備蓄量に10%程度の余裕を持たせる運用が推奨されます。
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
各災害備蓄品には、適切な管理方法があります。
たとえば、食料は「高温多湿、直射日光を避けて管理」が基本です。
また、賞味期限や有効期限が設けられているものもあります。
これらを確認してから、管理することも重要です。
確認を怠ると、発災時に利用できない恐れがあります。
賞味期限や有効期限が近づいたものは、新しいものと交換しましょう。
定期的に入れ替えることで、災害備蓄品を最適な状態に保てます。

ここからは、企業が用意しておきたい災害備蓄品を紹介します。
飲料水は、最も必要性が高い備蓄品です。
従業員の生命の維持に欠かせません。
目安としては、1日あたり3L/人を想定してください。
1.5Lサイズや2Lサイズのペットボトルだけでなく、500mlサイズのペットボトルも用意しておきましょう。
大きなサイズのペットボトルだけだと、コップがないときに口をつけて飲んだり、回し飲みをしたりしなければならないためです。
また、持ち運びにも労力を要します。
利用シーンに応じて複数サイズを揃えておくことが有効です。
食料も従業員の生命維持に欠かせません。
発災後に購入できない恐れがあるため、事前に準備をしておくことが大切です。
商品選択のポイントは、調理方法といえるでしょう。
電気やガスが止まっていることもあるため、簡便に調理できるものが適しています。
たとえば、水や湯を注ぐだけで調理できるアルファ化米、封を切るだけで食べられるレトルト食品などが挙げられます。
同様に、賞味期限にも注意が必要です。
賞味期限が短いと管理に手間とコストがかかります。
基本的には、3年以上の保存期間を有するものを選定するのが望ましいとされています。
衛生用品も用意しておきたい災害備蓄品です。
特に必要性が高い衛生用品として、簡易トイレが挙げられます。
発災時は、水道や電気が止まって既存のトイレを使えないことがあります。
尿意や便意を我慢し続けることはできないため、人数分の簡易トイレを用意しておくことが大切です。
使用済みの簡易トイレを、保管する方法も検討しておく必要があります。
女性従業員がいる場合は、生理用品も忘れずに用意しておきましょう。
備蓄量の目安は、1日あたり5~7枚程度(ナプキンの場合)です。
入浴できないことや下着を替えられないことを想定して、デリケートウェットシートやパンティライナーを併せて備えておくことが推奨されます。
発災時にケガをしたり体調を崩したりすることもあります。
医療機関をすぐに受診できない恐れがあるため、必要最低限の医薬品を用意しておくことも大切です。
具体例として、以下のものが挙げられます。
【医薬品の例】
持病がある従業員に、服用している薬を常備するように促しておくこともポイントです。
発災時は、普段よりも情報収集の重要性が高まります。
正確な情報をもとに、命を守る行動を選択しなければならないためです。
したがって、情報収集ツールも用意しておく必要があります。
具体例として挙げられるのが、災害情報を受信する防災ラジオです。
パソコンやスマートフォンも情報収集ツールですが、災害時は通信インフラの遮断で機能しないことがあります。
防災ラジオは、手動式や電池式などにわかれます。
管理の方法を踏まえて、確実に利用できる仕様・電源方式のものを選定することが重要です。
照明器具も優先度の高い災害備蓄品に位置づけられます。
発災時に、電気が止まることも考えられるためです。
用意していないと、夜間の避難や生活が困難になる恐れがあります。
照明器具の主な選択肢は以下の通りです。
| 種類 | 特徴 |
| 懐中電灯 | 小型で持ち運びしやすい。一方向を遠くまで照らせる。夜間の移動などに適している |
| ランタン | 広い範囲を明るく照らす。机などに置いて使用できる。室内灯に適している |
利用シーンにあわせて使い分けると快適性が高まります。
乾電池を忘れずに用意しておくことも大切です。
季節用品もできれば用意しておきたい災害備蓄品です。
主な季節用品として以下のものが挙げられます。
【季節用品の例】
持ち出し用袋などに災害備蓄品をまとめている場合は、季節の変化にともない季節用品の入れ替えが必要になることがあります。
避難生活に大きな影響を与えるため、忘れずに管理することが重要です。
以下の小物類を用意しておくと、災害に対応しやすくなります。
【小物類の例】
必要性の高い小物類は、ライフスタイルなどで異なります。
以上を参考に、必要品目の洗い出しと整備計画を進めることが重要です。

企業と家庭で、必要な災害備蓄品は異なります。
それぞれに必要な災害備蓄品は以下の通りです。
企業は、以下の点を重視して災害備蓄を行います。
【企業が重視する点】
また、企業は帰宅困難者への対応を求められます。
したがって、以下の災害備蓄品の必要性が高いと考えられます。
| 分類 | 具体例 |
| 帰宅困難者対策 | 飲料水、食料、寝具(寝袋など) |
| 衛生用品・生理用品 | 簡易トイレ、ナプキン、アルコール消毒、マスク |
| 安否確認 | 緊急連絡網、安否確認システム |
| マニュアル | 防災マニュアル、避難マップ |
組織で取り組む防災対策の一環として、災害備蓄品を準備することが大切です。
必要性が高い災害備蓄品は家族構成などで異なります。
それぞれの立場で、必要なものを検討することがポイントです。
用意しておきたい災害備蓄品の例を紹介します。
| 家族 | 災害備蓄品 |
| 高齢者 | 老眼鏡、補聴器、杖、成人用おむつ、入れ歯ウェットシートなど |
| 乳児・幼児 | 粉ミルク、哺乳瓶、ベビーフード、離乳食、スプーン、紙皿、紙コップ、紙おむつ、お尻ふきなど |
| ペット | ペットフード、キャリーバッグ、リード、トイレ用品、おもちゃ |
基本的な災害備蓄品などに加えて、これらのものが必要になります。
被災人数により、避難計画は異なります。
企業と家族が重視したいポイントは以下の通りです。
| 分類 | 重視したいポイント |
| 企業 |
|
| 家族 |
|
被災人数が多い企業は計画的な対応が必要です。
避難訓練を定期的に実施して、防災意識や対応力を高めておくことが求められます。
被災人数が少ない家族は、個別の対応を重視しましょう。
乳幼児や高齢者などへの配慮が必要です。
関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選
 災害備蓄品には、さまざまな種類があります。
災害備蓄品には、さまざまな種類があります。
ここでは、必要性の高い災害備蓄品の見極め方を解説します。
発災時の最優先事項は、従業員の命を守ることです。
以上を踏まえて、必要な災害備蓄品を見極めるとよいでしょう。
優先して準備したいものの例は以下の通りです。
【命を守る災害備蓄品】
飲料水と食料は、最低3日分が必要です。
食料は、簡単な調理あるいは調理不要で食べられるものが適しています。
まずは、これらを優先して準備することが求められます。
発災から72時間を境に、必要性の高い災害備蓄品は変化します。
この間は、救命活動と救助活動が優先されるためです。
また、時間の経過とともに、ライフラインの復旧も進みます。
発災から72時間は命を守るもの、以降は避難生活を維持するものの必要性が高まるといえるでしょう。
それぞれの時間帯で必要性の高い災害備蓄品は以下の通りです。
| 時間帯 | 必要性の高い災害備蓄品 |
| 発災から72時間以内 | 飲料水、食料、ホイッスル、簡易トイレ、軍手、ヘルメット、マスク、医薬品、防災ラジオ、モバイルバッテリー、懐中電灯、ランタン、毛布、防寒具など |
| 発災から72時間以降 | 着替え、衛生用品、生理用品、防寒具、防災ラジオ、充電器、簡易調理器具、現金、身分証、処方薬、常備薬 |
事業所に従業員が一時滞在する場合は、滞在期間を踏まえて必要性の高い災害備蓄品を見極めるとよいでしょう。
災害備蓄品の用途も、選定時に意識したいポイントです。
多用途に使えるものを優先的に選ぶと、コストや保管スペースを節約できます。
具体例として、以下のものが挙げられます。
| 災害備蓄品 | 用途 |
| ゴミ袋 | ゴミ袋、水の運搬、簡易用トイレ、防寒着、雨具 |
| ブルーシート | 敷物、簡易テント、部屋の間仕切り、ブランケット、雨よけ |
| 防災ラジオ | ラジオ、懐中電灯、充電器(機能は商品で異なる) |
まず多用途の物資を優先的に整備し、その後に不足品を洗い出すことで、無駄の削減につながります。
日常的に使うものと災害時に使うものの垣根をなくすことでも無駄を減らせます。
次のメリットなどを期待できるためです。
【メリット】
具体的な取り組みとして、普段使用しているレトルト食品やウェットシートを多めに購入するなどが考えられます。
必要な防災備蓄品の量を減らせる可能性があります。
持ち出し用と備蓄用で、災害備蓄の目的は異なります。
| 分類 | 目的 |
| 持ち出し用 | 避難時に従業員などの命を守る |
| 備蓄用 | 滞在先での生活を維持する |
したがって、優先するべきものも異なります。
それぞれの用途で優先したい災害備蓄品は以下の通りです。
| 分類 | 優先したいもの |
| 持ち出し用 | 500mlサイズの飲料水、1~2食程度の食料、簡易トイレ、軍手、マスク、ホイッスル、救急セット、懐中電灯、モバイルバッテリー |
| 備蓄用 | 3日分以上の飲料水、3日分以上の食料、衛生用品、生理用品、簡易調理器具、毛布、医薬品、ランタン、大容量のバッテリー |
防災備蓄の目的を踏まえると、必要なものを見極められるようになります。
 続いて、災害が発生する前に行うべき取り組みを紹介します。
続いて、災害が発生する前に行うべき取り組みを紹介します。
災害が起きる前に、避難場所や避難ルートを周知しておくことが大切です。
これらが曖昧だと、発災時に混乱を招いてしまいます。
建物の倒壊などで道が塞がれることもあるため、複数の避難ルートを設けておくこともポイントです。
避難訓練などでこれらを確認しておくと、発災時にスムーズに行動できます。
家族や従業員と、災害時の連絡方法を確認しておくことも欠かせません。
大規模災害の影響で、電話が不通になったり、通信できなくなったりすることがあるためです。
安否を確認できないと、事業の継続や復旧が難しくなります。
基本のポイントは、複数の連絡方法を定めておくことです。
主な連絡方法として以下のものが挙げられます。
【連絡方法の例】
これらの方法でも連絡できない場合に備え、集合場所を事前に定めておくことが重要です。
災害備蓄品の中には、賞味期限や使用期限を設けているものがあります。
定期的な見直しにより最適な状態を維持することが大切です。
この作業を怠ると、発災時に必要なものを使えない恐れがあります。
見直しのポイントは以下の通りです。
【見直しのポイント】
これらを継続的に行うことが重要です。
保管場所も事前に検討しておきたいポイントです。
よく考えずに決定すると、緊急時に取り出せなかったり、管理に手間がかかったりする恐れがあります。
以下の点を意識して、保管場所を決定することが大切です。
【ポイント】
保管場所を従業員に周知しておくことも必要です。
災害備蓄品の保管で問題になりがちなのが、賞味期限、使用期限切れによる廃棄です。
ローリングストック法を活用すると、この問題に対処しやすくなります。
基本的な取り組み方は以下の通りです。
【取り組み方】
定期点検・消費・補充のサイクルを継続することで、廃棄量を抑えつつ備蓄品の状態を最適に保てます。
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順
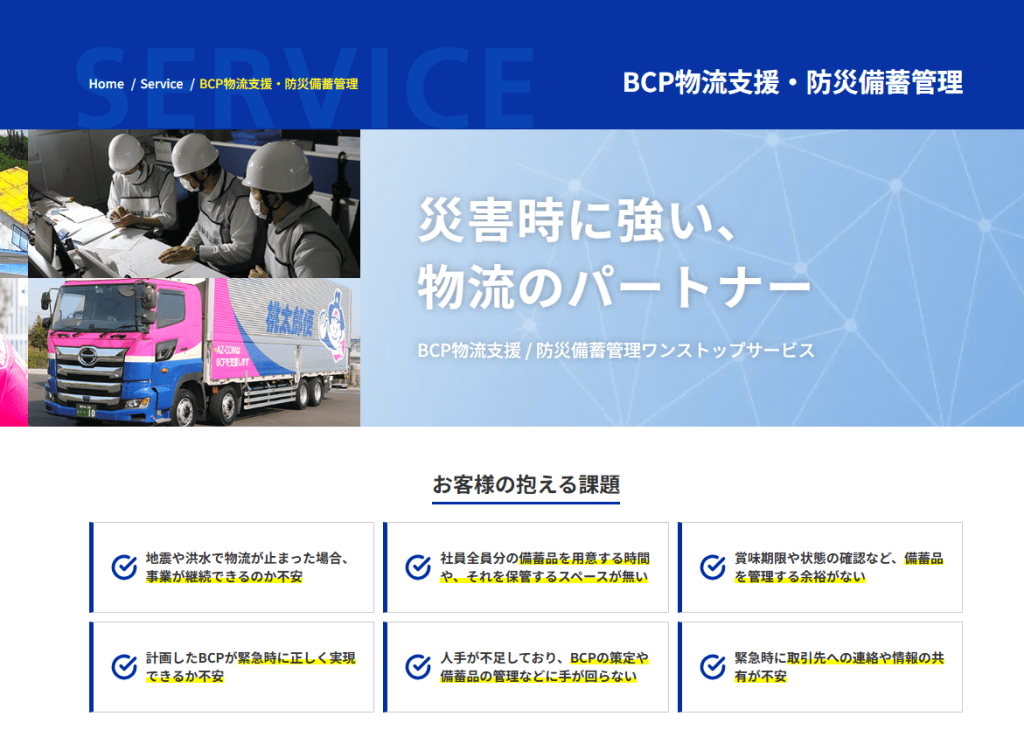
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。
「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。
 ここでは、企業の災害備蓄について解説しました。
ここでは、企業の災害備蓄について解説しました。
従業員の安全を確保するため、あるいは事業の継続性を高めるために、企業も災害備蓄品を揃えておく必要があります。
具体例として、飲料水、食料、情報収集ツールなどが挙げられます。
必要な備蓄量、適切な管理方法などを確かめたうえで、計画的に準備することが大切です。
自社のみでの対応が難しい場合は、丸和運輸機関の支援サービスを活用する方法もあります。
災害備蓄品の購入、買い替え、期限管理、保管などを一括でサポートする「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」などをご利用いただけます。
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
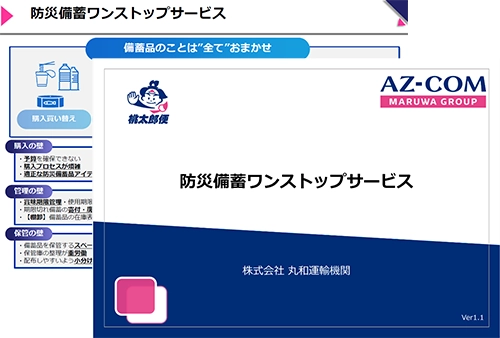 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中