-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

災害などの緊急事態に備えて、企業も保存食を備蓄しておく必要があります。
何をどの程度備蓄すべきかわからず、悩んでいる方もいるでしょう。
おすすめの保存食として、アルファ化米や缶詰パンなどが挙げられます。
いずれも長期保存に適している食品です。
ここでは、おすすめの保存食を紹介するとともに、保存食の備蓄量や管理のポイントなどを解説しています。
防災対策を検討している方は参考にしてください。
目次
 長期間にわたって保存できるように加工・処理された食料です。
長期間にわたって保存できるように加工・処理された食料です。
具体的な特徴は商品で異なりますが、3~7年程度、保存できるものもあります。
また、容易に調理できるものや簡単に持ち運べるものも少なくありません。
これらの特徴を生かし、緊急時の食料として活用されています。
具体例として、以下のものなどが挙げられます。
【保存食の具体例】
大規模災害などを想定して、保存食を備蓄する企業が増えています。
主な役割は、災害などでライフラインが止まったときに、被災者の生命を維持することです。
企業に保存食の備蓄を義務づける法律はありませんが、対応を怠ると労働者の安全への配慮を欠いているとみなされる恐れがあります。
労働契約法第5条で次のように定められているためです。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
企業の責任が問われる可能性もあるため、注意が求められます。
また、自治体が保存食の備蓄などに関する条例を定めていることもあります。
この点も事前に確認しておくべき事項の一つです。

保存食の多くは、以下の特徴を備えています。
【特徴】
これらの特徴について解説します。
保存食は長期間の保存を想定して開発された食品です。
具体的な賞味期限は加工方法などで異なりますが、数カ月~数年程度、保存できるものが多いでしょう。
緊急時にも備蓄品をすぐに食べられるため、非常時の食料として適しています。
頻繁に買い替える必要がないため、管理の手間を軽減できます。
数カ月に1回程度の頻度で賞味期限を確認すればよいため、管理の手間を減らせます。
保存食の多くは、ライフラインが止まった状態で利用することを想定しています。
したがって、容易に調理できるものや調理を不要にしているものが少なくありません。
代表例として挙げられるのが、缶詰やレトルト食品です。
缶を開けたり、封を切ったりするだけで美味しいご飯を食べられます。
あるいは、お湯やお水を注ぐだけで調理できるものもあります。
電気・ガス・水道が停止していても、保存食があれば食事の準備が可能です。
さまざまな選択肢がある点も特徴です。
主な種類として以下のものが挙げられます。
【主な種類】
各種類ごとに多様な商品が存在する点も特徴の一つです。
たとえば、アルファ化米には、白米、ドライカレー、チキンライスなどがあります。
事前に準備をすれば、緊急時でも充実した食生活を維持できる可能性があります。
軽量性や携帯性に優れた商品が多いことも特徴です。
量が増えても重くなったりかさばったりしにくいため、避難時に持ち出すときの負担を抑えられます。
緊急時の食料に適した特徴を備えているといえるでしょう。
ただし、具体的な重さは商品で異なります。
一部の商品は日常的に食べる食品と同程度の重量であるため、事前に確認が必要です。

続いて、保存食として活用したいおすすめの食品を紹介します。
長期保存を目的に開発された、水のみを原料とする清涼飲料水(食品衛生法におけるミネラルウォーター類)です。
一般的なミネラルウォーターより賞味期限(品質保証期限)を長く設定しています。
| 分類 | 賞味期限の目安 |
| 一般的なミネラルウォーター | 製造日から2年程度 |
| 保存水 | 製造日から5~10年程度 |
基本的な製法は一般的なミネラルウォーターと同じです。
両者の主な違いは、使用されるボトルの構造や素材にあります。
保存水はペットボトルの素材や厚みを工夫することで、長期間にわたり中身の蒸発や劣化を抑えています。
記載された容量を長期間にわたって維持できるため、一般的なミネラルウォーターよりも賞味期限が長く設定されているのです。
炊きたてや蒸したてのご飯を急速に乾燥させた保存食品です。
アルファ化は、水とともに過熱して柔らかくなったデンプンの状態を指します。
この状態を維持しているため、アルファ化米は水やお湯を注ぐだけで炊き立てのような状態に戻ります。
災害時に主食として活用できる食品の一つです。
賞味期限の目安は5年程度です。
おかゆ、わかめご飯、五目ご飯など、さまざまな種類があるため、従業員の好みにあわせて備蓄しておくこともできます。
パンを缶や袋に密閉した保存食です。
缶詰パンは、生地を缶ごと焼いて密閉するタイプと焼いたパンを缶に入れて密閉するタイプにわかれます。
前者のほうが、しっとりした仕上がりになります。
缶詰パン、袋詰めパンの主な特徴は以下の通りです。
【特徴】
賞味期限の目安は1~5年程度です。
袋詰めパンは、一般的にかさばりにくく、缶詰パンよりも保管しやすいとされています。
ただし、重いものをのせるとつぶれる恐れがあります。
凍らせた食品を、真空に近い状態で乾燥させた保存食です。
お湯や水を注ぐだけで簡単に調理できます。
主な特徴は以下の通りです。
【特徴】
フリーズドライの例として、カレー、パスタ、みそ汁、スイーツなどが挙げられます。
選択肢の多さも魅力といえるでしょう。
賞味期限の目安は1~3年程度です。
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順
気密性のある容器に密閉した食品をレトルト釜(高圧釜)で殺菌した保存食です。
レトルト食品は以下の特徴を備えています。
【特徴】
1960年代(国内)から扱われているため、商品のバリエーションが多い点も魅力です。
賞味期限の目安は、1~2年程度といえるでしょう。
緊急時の利用を想定し、賞味期限が6〜7年程度に設定されている商品も存在します。
ビスケット・クッキーも、保存食として活用できます。
主な特徴は以下の通りです。
【特徴】
手間をかけずにエネルギーを補給できる点が魅力です。
お菓子として食べれば気分転換にもなります。
クリーム入り、チョコチップ入りなど、さまざまな商品が販売されているため、好みにあわせて備蓄しておくこともできます。
賞味期限の目安は、5~7年程度といえるでしょう。
必要に応じて、アレルギー対応食品を用意しておくことも重要です。
食物アレルギーのある方が特定のアレルゲンを摂取すると、急性のアレルギー反応によって命に関わる可能性があります。
アレルギーに関するアンケートなどを実施してから、保存食を用意するとよいでしょう。
同様に、ハラール対応食品についても検討が必要です。
ハラール対応食品は、イスラム教の戒律で「許された食べ物」を指します。
豚肉やアルコール飲料は禁じられています。
専門的な知識がない場合は、ハラール認証を受けた商品を選択するのが適切です。
 現在のところ、企業に防災備蓄を義務づける法律はありません。
現在のところ、企業に防災備蓄を義務づける法律はありません。
しかし、内閣府が発表している「事業継続ガイドライン」で、緊急時対応として備蓄の活用が挙げられています。
備蓄品の品目、数量について、自治体の条例などを参考にする旨が記載されている点もポイントです。
たとえば、東京都は「東京都帰宅困難者対策条例」で企業に対して、以下の努力目標を定めています。
事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
法的な義務があるわけではありませんが、企業においても防災備蓄の必要性が高まっているといえるでしょう。
内閣府「事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応- (令和5年3月)」

企業が用意する保存食の備蓄量は、従業員の人数×3日分が目安です。
保存食別に備蓄量の目安を紹介します。
| 保存食の種類 | 備蓄量の目安 |
| 水 | 3リットル/日×3日間=9リットル |
| 主食 | 3食/日×3日間=9食 |
東京都は、来社中の顧客が被災することなどを想定して、10%程度の余裕をもって備蓄しておくことを勧めています。
たとえば、従業員の人数が10名であれば、水99リットル、主食99食が目安といえるでしょう。
実際の備蓄量は、以上を参考にオフィスの特徴などを踏まえて決定します。

続いて、保存食を管理する際に意識したいポイントを解説します。
保存食を用意する前に、必要量を把握することが大切です。
この作業を怠ると、保存食が全従業員に行き渡らなかったり、不足してしまったりする可能性があります。
ここでいう従業員は、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、オフィスで働くすべてのスタッフです。
また、来社中の顧客が対象に加わることもあります。
数量に多少の余裕をもたせておくことが重要です。
関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認
さまざまな種類の保存食を用意しておくことも大切です。
被災時は、食事が唯一の楽しみになりえます。
同じものが続くと、食事に飽きてしまう恐れがあります。
ストレスの増加につながる可能性があるため、留意が求められます。
たとえば、ご飯だけでなくパンや麺類、またクッキーや羊羹などのデザートを用意することが挙げられます。
保存食には賞味期限が設定されています。
定期的な入れ替えが必要です。
処分のルールを決めておくと、スムーズに入れ替えられます。
管理方法にも注意が必要です。
部屋が空いているからなどの理由で、十分に検討せずに保管場所を決めると、什器の転倒により保存食を取り出せなくなったり、水濡れのリスクが生じたりする可能性があります。
緊急時であっても、確実に取り出せる場所に保管しておくことが大切です。
また、保管場所を周知して誰もが確実に利用できるよう、周知徹底しておくことが不可欠です。

保存食の管理では、食品の廃棄が課題になりがちです。
ここでは、その対策を紹介します。
賞味期限切れによる食品廃棄を抑えるには、ローリングストック法を導入するのが効果的です。
具体的な取り組み方は次の通りです。
【取り組み方】
備蓄を循環させるため、ローリングストック法と呼ばれています。
この方法であれば、賞味期限切れの廃棄を減らせます。
また、備蓄しているものを食べることで、味や実用性を事前に把握できる利点もあります。
関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順
ローリングストック法を活用したとしても、保存食の管理には一定の手間がかかります。
賞味期限のチェックや買い替え作業に人員を割けないこともあるでしょう。
自社での対応が難しい場合は外部へ委託できます。
一例として挙げられるのが、丸和運輸機関が提供している「防災備蓄管理ワンストップサービス」です。
同サービスでは、平時の防災備蓄管理を一括サポートしています。
具体的なサポートの範囲は次の通りです。
【サポートの範囲】
保管だけでなく物流も委託できるため、保存食の管理業務にかかる負担を大幅に軽減できます。
適切に管理することで、保存食を常に使用可能な状態に維持できる点も利点です。
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。
「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。
 ここでは、大規模災害などの緊急時に備える保存食について解説しました。
ここでは、大規模災害などの緊急時に備える保存食について解説しました。
保存食の主な特徴は、長期保存が可能であることと、調理が容易であることです。
おすすめの保存食として、アルファ化米、フリーズドライ、レトルト食品が挙げられます。
ただし、賞味期限が設けられているため、定期的な入れ替え作業が必要となります。
保存食の管理には、一定の工数と注意が必要です。
自社での管理が難しい場合は、丸和運輸機関にご相談ください。
防災備蓄管理を一括でサポートする「防災備蓄管理ワンストップサービス」や防災備蓄をサブスクリプション形式で提供する「あんしんストック」などのサービスを利用できます。
丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する
「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
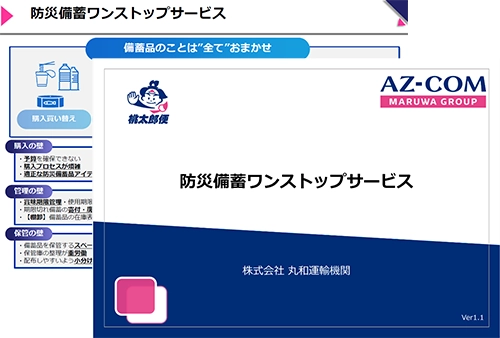 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中