-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶など突発的な経営環境の変化等不測の事態が発生しても重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させる、つまり確実な事業継続を実現するためには、BCMS、BCMが不可欠です。
それは、組織の事業継続能力を維持・向上するための組織管理行為こそがBCM(Business Continuity Management)だと言えるからです。
ここでは、BCMSやBCM、BCPの関係をまとめ、国内外の認証制度について紹介します。
また、国内外の認証制度を取得するメリットをまとめましたので、御社に合う認証制度を活用すれば事業継続力の強化を図り、BCMに取り組むことができます。
目次

BCMS(Business Continuity Management System)事業継続マネジメントシステムは、事業継続を実現するためのマネジメントシステムのことを指します。
事業継続力を維持・向上させるための組織管理を行うには、管理の枠組み(継続的改善を実施する組織内のプロセスやルール)を定める必要があります。
BCMSとは組織管理を実施するための、組織に適したプロセスやルールのことです。各組織におけるBCMSは、組織の事業継続能力を維持・向上させるために最適なものが構築されることが望ましいとされています。
ISOにおけるBCMSは、様々な手法の中でISOとして推奨する一つのモデルです。
ISOのBCMSを使用しなくても、自社の文化に合ったマネジメントシステムを使用して事業継続力を維持・向上させていれば、それは立派なBCMと言えるでしょう。

BCM(Business Continuity Management)事業継続マネジメントは、事業継続を実現するためのマネジメントそのものを指します。
例えば、BCP策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、事前対策の実施、取組を浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動など、経営レベルの戦略的活動として位置付けられています。
ただし、BCMの内容は自社の事業内容、規模などに応じて経営者がその範囲を判断してよいものです。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?取り入れるメリットと確認すべき注意点
関連記事:BCP対策に適したオフィスビルの選び方と環境づくりのポイント
| 項目 | BCP (Business・Continuity・Plan) |
BCM (Business・Continuity・Management) |
|---|---|---|
| 訳 | 事業継続計画 | 事業継続マネジメント |
| 内容 | 緊急事態が発生した際にいち早く事業を復旧させ、事業を継続させるための計画 | 事業を継続させるための計画であるBCPを策定し、維持・改善するためのプロセス |
| 目的 | できる限り事業を中断させることなく、迅速に復旧のための対策を取ること | BCPのための体制を確立してそのための維持や管理を行うこと |
BCP(事業継続計画)によって事業継続能力を維持・向上させるための取り組みがBCM(事業継続マネジメント)であり、BCP(事業継続計画)を組織管理ための方法がBCMS(事業継続マネジメントシステム)です。
関連記事:BCP(事業継続計画)策定のステップと押さえておきたいポイント

英国規格協会(BSI)から2007年11月発行されている事業継続マネジメントに関する国際規格です。
国際標準化機構(ISO)によるBCMS(事業継続マネジメントシステム)に関する国際規格です。
ISOのBCMSは、ISOが規定する「組織のマネジメントシステム」の中で事業継続を担う部分という位置づけとなっています。
組織の潜在的な脅威、及びそれが顕在化した場合に引き起こされる可能性がある事業活動への影響を特定し、主要なステークホルダーの利益、組織の評判、ブランド、及び価値創造の活動を保護する効果的な対応のための能力を備え、組織のレジリエンスを構築するための枠組みを提供する包括的なマネジメントプロセス
BCMを導入し、維持するための適切な資源が提供され、トップマネジメントによって支援される、継続的なマネジメント及び統治のプロセス
| 箇条 | 項目 | 記載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 適用範囲 | ISO22301の趣旨や適用可能な範囲 |
| 2 | 引用規格 | ISO22301で引用している文書 |
| 3 | 用語及び定義 | その他用語に関する説明 |
| 4 | 組織の状況 | 組織やその状況の理解、利害関係者の人数など組織に関する理解 |
| 5 | リーダーシップ | リーダーに求める責任や従業員の参加を定める事項 |
| 6 | 計画 | 事業継続目的やそれを達成するための計画策定など |
| 7 | 支援 | 資源、力量、認識などBCMS運用に必要となるもの |
| 8 | 運用 | BCMS運用の計画・管理、リスクアセスメントに関することなど |
| 9 | パフォーマンス評価 | 4~8章の要求に関する取り組みの評価 |
| 10 | 改善 | パフォーマンス評価の結果に基づいた改善について |

BCP策定の動機が、顧客からの要求である場合は少なくありません。
顧客企業は、外部委託によって自社の努力だけでは事業復旧が困難になってしまったり、サプライチェーンが拡張・延長することで平時には順調な物流網が災害や感染症の蔓延などをきっかけに滞ったりすると、顧客企業の社会的責任を果たすことができなくなります。
確実なサプライチェーンを構築するために納入業者にBCP策定や事業継続への取り組み状況を求めることは、昨今の企業のコンプライアンス、CSR等の社会的要求や信頼性確保の要求、期待の高まりとも言えます。
関連記事:BCP(事業継続計画)策定のステップと押さえておきたいポイント
行政、産業界、消費者団体等から、被災しても重要な物品、サービスの供給責任を果たすべきとの議論が高まっています。
災害時の地域社会との連携や貢献は、企業側にも積極的な対応が求められています。
内部等瀬への取り組みにより、コーポレートガバナンスの強化が法令により求められており、この取り組みは事業継続と密接な関係にあります。
日本銀行考査局が「金融機関における業務継続体制の整備について(2003年7月)」を発行しました。
金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書(第3版)が発行されました(緊急時対応計画)。

顧客企業から事業継続に関する取り組みを求められた際にあると安心なのが、国内外の認証制度です。国内外の認証制度を取得難易度別に3つ紹介します。
事業継続力強化計画認定制度とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。中小企業のための取り組みやすいBCPと位置づけられます。
認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの措置が受けられます。令和7年2月現在、日本国内で認定を受けている企業は75,528社です。
申請をすることができるのは中小企業となりますが、BCPを初めて策定する場合には大変取り組みやすい制度となっています。顧客企業からBCP対策を求められた際、BCPを持っていない中小企業がまず取り組むべき事項と言えるでしょう。
申請書類を作成し終わってからの標準処理期間は45日と、スピーディーです。一方、各地方経済産業局からの紹介など、審査に時間を要する場合もありますので、余裕を持った申請をお勧めします。
・事業継続力強化の必要性を認識すること
・脅威と発生時の被害発生の認識をすること
・必要な事前対策(防災+事業継続、訓練の実施を含む)の抽出と実施計画策定
・初動対応体制と考働プロセスの明確化(人命安全確保、被害状況把握、顧客報告)
中小企業防災・減災投資促進税制:特別償却16%
自然災害への対策を強化する為、令和9年3月31日までに事業継続力強化計画に対象設備の投資を行うことを記載して認定を受けた中小企業が認定後1年以内に予定した設備導入を行った場合に特別償却16%を適用できる。
| 減価償却資産の種類(取得価格要件) | 対象となるものの用途または細目 |
|---|---|
| 機械及び装置 (100万円以上) |
自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等 (これらと同時に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に機能を有するものを含む) |
| 器具及び備品 (30万円以上) |
自然災害などの発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するすべての設備 |
| 建物付属設備 (60万円以上) |
自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水版、耐震・制震・免震装置、架台(対象設備をかさ上げするために取得等するものに限る)、防水シャッター等 (これらと同時に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に機能を有するものを含む) |
中小企業防災・減災投資促進税制の対象となるものの導入に関してご相談があれば、丸和運輸機関にお問い合わせください。
・日本政策金融公庫による低利融資(BCP資金)
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
事業継続力強化認定事業者は、以下予算事業において、加点措置を行けることができます。
また、被災した場合における復旧等の費用を補助する予算事業の申請の際には、事業継続力強化計画の認定が求められます。
・ものづくり補助金
・事業継承・引継ぎ補助金(経営革新事業・専門家活用事業)
・中小企業省力化投資補助金(一般型)
・地方公共団体による小規模事業者等支援推進事業費補助金(災害時支援)
・なりわい再建支援補助金
事業継続力協会制度認定を取得すると、中小企業庁のホームページに「事業継続力強化計画」認定企業一覧」として企業名とホームページのリンクを公表できます。
事業継続力協会制度認定を取得したら、ロゴマークを使用することができます。名刺や会社ホームページに掲載・活用することで、BCPに熱心に取り組み姿勢を社会から評価されるでしょう。
事業継続力強化計画認定は初任者にも取り組みやすい認定制度ですので、中小企業でBCP策定に挑戦しようとしている企業はぜひ「中小企業庁 事業継続力強化計画」で申請方法をチェックしてみてください。

内閣官房国土強靱化推進室では、国土強靱化に資する民間企業等の取組みを促進するため、平成28年度より事業継続に積極的に取り組んでいる企業等を「国土強靱化貢献団体」として第三者(レジリエンスジャパン推進協議会)が認証する仕組み(レジリエンス認証)を運用しています。
令和4年11月末までに、計285団体(うち「+共助」は180団体)が認証されています。
①事業継続の方針策定、②同分析・検討の実施、③同戦略・対策の検討と実施、④具体の計画策定、⑤見直し・改善の仕組み、⑥事前対策の実施、⑦教育・訓練の実施、⑧担当者の経験と知識、⑨重大な法令違反がない
申請担当者の経験と知識が求められ、経営陣のコミットメントも評価される認証となりますので、中小企業強靭化法に基づく事業継続力強化計画認定制度と比べて取得の難易度は高いと言えるでしょう。
年に3回、申し込みを受け付けています。募集開始からおよそ4か月で取得・登録手続きが完了します。
募集期間はおよそ1か月半、その後一次審査(書類提出)及び二次審査(面接)が行われます。
取得のメリットとしては全部で5つあります。
取得のメリット1:一部金融機関で優遇制度がある(ローン利率の引下げ、長期間の融資、災害時発動型保証等)
<主な取扱例> (詳しくは各銀行、協会HPをご覧ください)
取得のメリット2:事業継続に関する取組みを専門家に評価してもらうことで、更なる改善につながります。
取得のメリット3:レジリエンスジャパン推進協議会のホームページや内閣官房国土強靱化推進室のホームページに認証取得団体として公表されます。
取得のメリット4:レジリエンス認証ロゴマークを名刺や広告等に付して、自社の事業継続や社会貢献への積極的な姿勢を顧客や市場に対してPRすることができます。
また、社会貢献に積極的に取り組む企業には、「レジリエンス認証 事業継続及び社会貢献」ゴールドロゴの取得が可能です。
大規模自然災害等に際しては、個々の企業等の自助のみならず、社会全体での共助を最大限機能させることが重要であることから、「国土強靱化貢献団体」のうち、社会貢献に積極的に取り組んでいる企業等を「国土強靱化貢献団体(+共助)」として認証する仕組みを平成30年度に追加しています。
取得のメリット5:関東地方整備局管内の建設会社は、追加の書類を提示することにより、関東地方整備局「建設会社における災害時の事業継続力(企業BCP)認定」をあわせて受けることができます。
ISO22301とは、国際標準化機構(ISO)によるBCMS(事業継続マネジメントシステム)に関する国際規格です。
ISO22301の認証取得を目指す際には、2度の認証審査を受けなければなりません。審査は、以下の2種類です。
| 審査段階 | 内容 |
|---|---|
| ファーストステージ審査 | 文章審査を中心としたものであり、事業計画のほか、リスクアセスメントなどの文書や記録に関連した審査が行われる。 また、ファーストステージ審査時点でセカンドステージ審査のために必要な情報収集を行う。 |
| セカンドステージ審査 | 内部審査とマネジメントレビューを終了した上で受ける検査。現在どういったマネジメントシステムが実施されているのか評価を行う。 |
原則としてファーストステージ審査とセカンドステージ審査の間隔は、最短で1か月、最長6か月となっています。
・複数の拠点や部門を持つ企業は、組織全体で同じ一貫したアプローチを取ることができる。
・顧客、サプライヤー、規制機関、その他の利害関係者に対して、事業継続のための適切なシステムとプロセスが整っていることを明示することで、安心して取引をしてもらうことができる。
・ビジネスパフォーマンスと組織の回復力(レジリエンス)の向上。
・重大な課題や脆弱性の領域を分析し、事業への理解を深めることができる。
・その他、組織がどのように運営されているかを明確かつ詳細に示し、戦略的計画、リスク管理、サプライチェーン管理、事業変革、リソース管理に資する貴重な洞察を提供します。
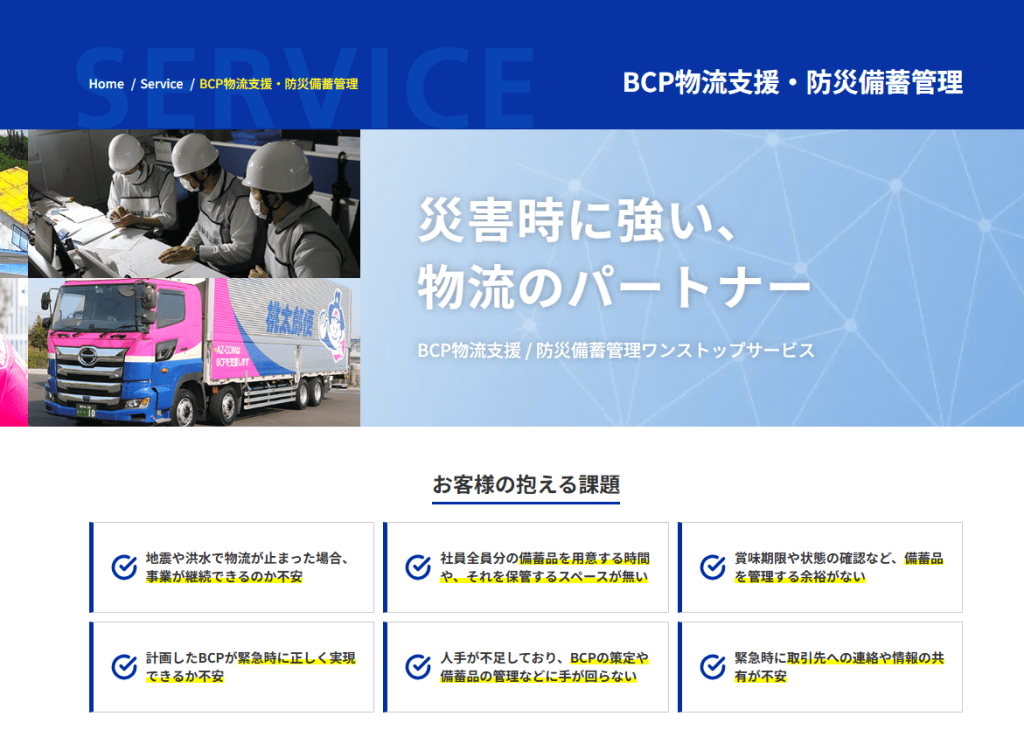
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。
災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

BCMS(Business Continuity Management System)事業継続マネジメントシステムについて解説しました。BCP・BCMとの関係、更にISO22301やBS25999といった事業継続におけるマネジメントシステムの各流派についても紹介しました。
BCPは策定しただけでは不十分です。BCPの策定をきっかけに、事業継続力向上の為BCMに取り組んで行きましょう。
事業継続におけるキーワードの一つに「代替戦略を持つこと」があります。事業継続のために必要なリソース(例えば、人、物資、機材、在庫)を代替拠点に移転することをお考えの場合は、丸和運輸機関にご相談下さい。BCPに関する問題や課題をワンストップで解決可能なBCPトータルソリューションを展開しています。
BCP物流支援サービスなら丸和運輸機関にお任せください。
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する
「BCP物流支援サービス」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
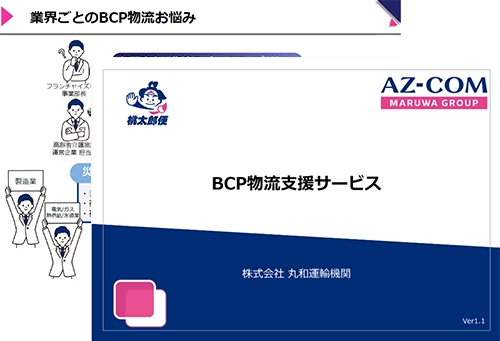 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中