-
企業情報
Company -
事業紹介
Service- AZ-COM 3PL
- 輸配送サービス 桃太郎便
- その他サービス
- BCP物流支援・防災備蓄管理
- 投資家情報
IR - 採用情報
Recruit - お問い合わせ
Contact

予測できない非常事態が発生した場合、それによって事業の継続が困難になることがあります。特に企業がリスクマネジメントに取り組むにあたり、不可欠とされているのがBCPです。
ここでは、BCP対策とは何か知りたいと考えている方のため、防災との違いや必要な理由、どういった要素を検討していくべきなのかなどについて解説します。BCP対策に取り組むことによって得られるメリットを知りたいという方はぜひ参考にしてください。
目次

BCP対策とは、自然災害や感染症の拡大、テロ、サイバー攻撃などによる非常事態に備え、できるだけ被害を抑えたうえで事業継続を目指すための対策のことをいいます。
BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取ったものであり、
企業は、災害、事故、感染症、その他の事象による被害を受けても、取引先等の利害関係者や社会から、重要業務が中断しないこと、中断してもできるだけ短い期間で再開することが望まれています。
この実現を目指す計画が、「事業継続計画」(BCP:Bushiness Continuity Plan)です。このBCPによって「顧客の他社への流出」、「マーケットシェアの低下」、「利益や売り上げの低下」、「企業の評価の低下」等の問題をまぬがれようとするのです。
BCPには非常事態が発生した際の方針や対応手順などがまとめられています。企業にとっての非常事態はいつ発生するのか予測できません。そのため、どのタイミングで予期せぬ問題が発生しても迅速に対応できるよう、BCPの策定が求められます。
日本は地震が多い国として知られており、大震災発生時には、事業に甚大な影響を及ぼす可能性があります。万が一に備えた対策の準備が不可欠です。
関連記事:BCPは誰が作るべき?担当者に求められるスキルと具体的な策定方法
BCP対策と混同されやすいものとして、防災が挙げられます。防災は、その名の通り災害を防止することであり、地震や台風、火事といった万が一の災害に備えて人命や財産を守ることが目的です。従業員の安全や建物設備に被害を出さないことなどを重視しています。
一方で、BCP対策は事業の継続を目的とした取り組みです。防災では基本的に自社の従業員や資産を守りますが、仮に調達元や供給元の被害が大きかった場合、事業を継続することは困難です。
BCP対策ではこういった広い範囲で物事を考え、何らかの非常事態が発生した際でも事業継続を目指します。もちろん、その中には人命や設備を守ることも含まれているのが特徴です。
BCMとは「Business Continuity Management」の略であり、日本語に訳すと「事業継続マネジメント」となります。一方、BCPは日本語で「事業継続計画」であり、緊急事態に備えて計画を立て、それを運用するための計画です。
策定したBCPが実際の現場で活用できるように体制をマネジメントするのがBCMと考えるとわかりやすいでしょう。つまり、BCPはBCMの一部分ともいえます。
BCPは策定するだけでは、非常事態に対応できない可能性があります。これを防ぐためには、定期的に訓練を行ったり、従業員に対して理解を深める取り組みをしたりすることも必要です。必要に応じて改定を繰り返していくことになりますが、このサイクルがBCMです。
IMPは「Incident Management Plan」の略であり、日本語では「初動対応計画」と訳されます。緊急事態が発生した際、被害を最小限に抑えるには、迅速な初動対策に取り組まなければなりません。その際に実施すべき対応を示した計画のことがIMPです。
また、BRPとは「Business Recovery Plan」の略で、日本語だと「事業復旧計画」や「事業回復計画」と訳されます。IMPで初動対応を計画し、事業の維持や継続に関する部分はBCPで策定、その後必要となる復旧に関することをBRPとして計画する流れとなります。
なお、これらを総合したものも広義でのBCPといえます。IMPもBRPもBCPのために必要なものの一部と考えておきましょう。
関連記事:BCMSとは?BCP・BCMとの関係と国内外の認証制度

BCP対策が求められる大きな理由は、事前に何も対策を考えていなかった場合や緊急事態が発生した際に、事業の継続が困難になるためです。
たとえば、復旧が長引いてしまえば業績の悪化につながりやすく、その結果事業継続が難しくなるでしょう。自社で働いてくれている従業員を継続的に雇用できなくなれば、従業員にも大きな迷惑をかけることになります。
もちろん、取引先にも迷惑をかけることは防げません。企業のイメージが低下すれば、倒産のリスクが高まります。BCP対策をとることは企業の倒産リスクを抑えることにもつながるので、すべての企業にとってBCP対策は不可欠といえるでしょう。

BCP対策ではどのような要素について検討していく必要があるのでしょうか。特に重点的な対策が求められるのは、以下の3つです。
BCPで対策が必要なのは、企業にとって非常事態とも呼べる状況につながるリスクです。自然災害に関することだけではなく、外的要因や内的要因についても検討する必要があります。
具体的なリスクは各社で異なるので、自社にとって想定されるリスクを、早期に明確化しておくことが重要でしょう。

BCP対策をしなければならないことは理解しているものの、何となく先延ばしにしているケースもあるのではないでしょうか。ですが、BCP対策を実施していくことにより、企業にはさまざまなメリットがあります。代表的なメリットは以下の5つです。
何らかの緊急事態が発生した際、事前に備えて対応策を計画しておくのと全く何も準備していないのとでは、企業が受ける被害が大きく変わってきます。BCP対策を講じることで、事業停止のリスクを最小限に抑え、復旧までの対策も明確にしておくことが可能です。
事業が停止している期間が長くなるほど事業の再開は難しくなってしまいます。できる限り緊急時にも対応できるよう、BCP対策によって備えることが重要です。
中核事業とは、会社を存続させていくうえで最も重要な事業、または緊急性の高い事業のことをいいます。緊急事態が発生した際は、通常通りの業務継続は困難です。そのため企業にとって停止するわけにはいかない中核事業に人員や設備を注力していくことになります。
BCP対策をとることで、自社にとって何が中核事業であるかを調べることになるので、自社の中核事業を可視化できる点も、BCP対策を行う上での重要なメリットです。
また、中核事業を維持するうえでどういったリスクに備えなければならないのかも見えてくるので、リスクを理解して事業継続の基盤強化にもつながります。
特に大規模な災害が起こった際は、多くの企業が影響を受け、場合によっては事業を継続できなくなることもあります。そのような状況下でもBCP対策によって事業継続ができれば、取引先や株主などのステークホルダーからの信頼を獲得することにつながります。
事業が停止した場合は取引先にも影響するので、一度失った信頼を回復するのは困難です。反対に事業を継続できれば大きな評価につながるので、それを機に新たな取引先の獲得につながる可能性もあります。自社の評判にもつながるので、BCP対策は企業経営において不可欠といえるでしょう。

BCPを策定する場合は、事前に策定の方針を決めてから優先すべき事業・リスクを考える、事業継続戦略を検討する、具体的な計画を策定するといった形で進んでいきます。
それぞれの手順で行うべきことは以下のとおりです。
BCP策定をどのような方針で進めていくか明確にしておきます。その際は、自社で掲げている経営理念や経営方針といったものを基準として考えると良いでしょう。方針を定めておくことで、後に明らかになるリスクに対して適切な対策を検討しやすくなります。
また、緊急時は従業員が自己判断で対応しなければならないこともありますが、そういった場合も全体の方針を定めておけば自己判断しやすくなるでしょう。
具体的な方針の例としては「何よりも従業員と家族の安定を最優先する」「顧客の信用を維持する」などが挙げられます。自社に合った基本方針を決定しておきましょう。
BCP策定に関する方針を決めておくと、その方針で進めていくためにはどの事業を優先すべきか判断する助けになります。
たとえば、自社の利益よりも顧客からの信用を維持することを優先する場合は、顧客対応に力を入れる形になるでしょう。
BCPは事業を継続していくために立てる計画なので、基本的には、自社の存続に直結する中核事業を優先する必要があります。優先的に取り組むべき事業については、災害の規模や種類に応じても臨機応変に対応しなければなりません。
そのためには、自社の場合はどのようなリスクが考えられるのか絞り込んでおきましょう。最もリスクの高いものから対策方法を検討していきます。
事業を継続していくうえで必要な戦略について検討します。先に決めておいた優先的に取り組むべき事業において、目標とする復旧時間や復旧レベルを定めておきましょう。
次に、事業継続のために必要な対策を策定していきます。復旧時間・復旧レベルについて考える際は、自社のことだけではなく取引先のニーズも踏まえたうえでの検討が必要です。
想定される被害からどのようにして自社の事業を守るのか、災害などによって利用・入手できなくなったものはどういった形で代わりを用意するのか考えておきましょう。
なお実際の非常事態では何が起こるかわからないので単一の対策や戦略に依存せず、代替案も併せて検討することが重要です。
基本的な戦略が決まったら、続いて具体的な計画の策定に移ります。「できればこうしたい」「こうなれば理想的」と考えるのではなく、実現可能な計画を策定することが重要です。
たとえば、復旧までに必要な日数を誤って短く見積もってしまえば、事業再開の見通しにもずれが生じる可能性があります。全体を大きく考えるとわかりにくくなるので、各復旧作業や業務ごとに細かく分けて行うべき対応を検討していきましょう。
また会社の体力も含めて考慮する必要があります。たとえば、事業が3か月以上の停止で事業継続が困難となる場合には、3ヶ月以内に事業再開を目指すための具体的な計画を策定していくことになります。

BCPを策定する際には、事前に確認しておきたいポイントがあります。ここでは、特に重要なポイントを4つ紹介するので、可能であればすべて実施していきましょう。
策定したBCPは継続的にブラッシュアップを行っていきます。はじめから完璧な形でBCPを策定することは不可能ですので、見直しが必要なポイントがないかを確認していきましょう。
たとえば、BCPを策定したあとにさらに良い復旧対策などを思いつくこともあるはずです。他社の事例などを参考にすると新しいアイディアも出てきます。自社でBCPを策定した際にはなかった便利なBCP支援サービスが出てくることもあるでしょう。
こういった情報を収集しながら必要に応じてBCPの内容を更新していくことが欠かせません。放置すると内容が古くなり、実際の緊急事態時に活用できない恐れがあるため、注意が必要です。
BCPの策定は、実際にBCP発動時に現場で指揮をとる人や対策本部長となる人が中心となって行っていくことになります。しかしBCP発動時は会社全体で取り組んでいかなければならないため、全ての従業員にBCP対策を定着させておくようにしましょう。
基本的な対策は、社内研修や策定したBCP対策に基づく訓練の実施です。実際にBCP発動時と同様の訓練を行うことにより、企業全体で動いた際の不備が明らかになります。
一度だけの訓練ではなく、定期的に実践していきましょう。また社内報にBCP対策の詳細を掲載しておき、一人ひとりの従業員に確認するよう促す方法もあります。
BCP対策は自社に合った形で検討していかなければなりません。ただし実際にBCPを策定ようとした時に、つまずいてしまうようなこともあるでしょう。こういった場合は、BCPのガイドラインやマニュアルを参考にするのがおすすめです。
たとえば、内閣府の防災担当が公表している事業継続ガイドラインがあります。(※)
こちらは業種や業態、希望などを問わず、すべての企業や組織を対象としたものです。具体例が掲載されているので、参考になります。
他にもBCP対策マニュアルを配布している業界団体があるので、自社に合ったものを選んで参考にしましょう。同業他社がどのような対策をとっているかを調べるのも参考になります。
※参考サイト:【PDF】内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和5年3月)」
新型コロナウイルス流行による影響は記憶に新しく、多くの企業が打撃を受けました。今後、同様の感染症が再び拡大する可能性もあります。各企業では、自社で講じるべき感染症対策を事前に検討しておきましょう。
もし、従業員の間で感染症が広がってしまった場合、通常業務の継続が困難になります。テレワークなどに対応していなければ、事業全体の業務がストップしてしまうことがあります。
このような事態を防ぐためにもBCP対策の中で感染症対策について検討を進める必要があります。感染症の拡大を防ぐための対策だけではなく、仮に感染が広がってしまった場合はどのように事業を継続していくのか考えておきましょう。
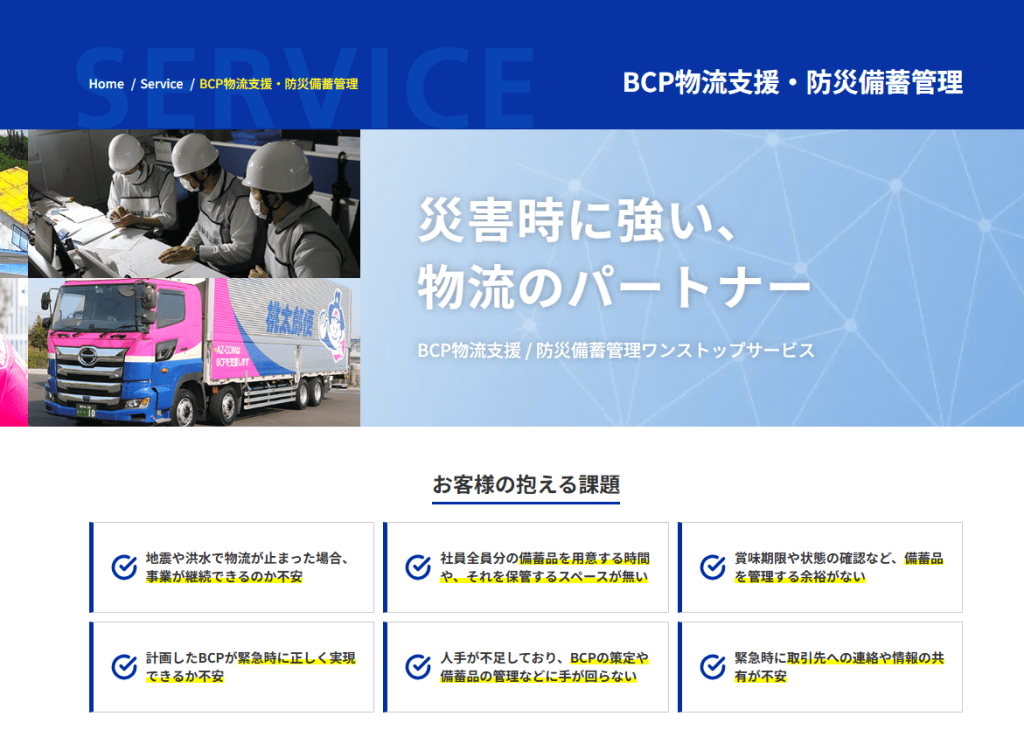
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。
災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。
詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

いかがだったでしょうか。BCP対策とは何か、防災とは何が違うのかなどについて解説しました。BCP対策を実施するメリットもご理解いただけたでしょう。
BCP対策を実施すべきなのは大手企業だけではありません。事業継続が困難になることを防ぐためにも、積極的に実施していくことが大切です。
災害などの非常事態が発生した際、物流が滞ると困る事業を行っている方もいるでしょう。そういった方は、ぜひ株式会社丸和運輸機関のBCP物流支援サービスをご利用ください。非常事態でも物流をストップせずに済むような「BCP物流支援サービス」を提供しています。平常時から万が一に備えておきたい方は一度ご相談ください。
丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する
「BCP物流支援サービス」を提供しています。
以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、
BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。
BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。
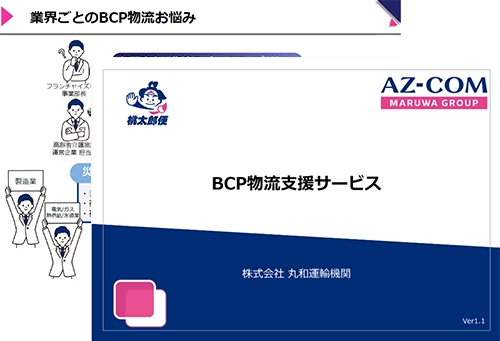 無料で資料請求 →
無料で資料請求 →
物流支援・防災備蓄でお困りの方へ
BCP対策のすべてが
詰まった資料を配布中